ペットの命を守るための遺言書・契約書の種類と作成方法

昔の日本では、犬や猫は家族というより、ただの飼い犬や飼い猫というポジションでした。
しかし、現在では家族の一員として猫や犬と接し、お世話を通じて大きな幸せを感じる人が増えています。
その一方で、獣医療や飼育環境の改善によりペットの寿命が延び、飼い主さんよりもペットの方が長生きするリスクに備える必要が出てきました。
日本の法律では、ペットは「物」として扱われます。
たとえ家族として長年一緒に暮らしてきたとしても、人と同じように財産を相続することはできません。
高齢で1人暮らしの飼い主さんがペットより先に亡くなられた際、何の生前対策も行われていないと、最悪の場合にはペットの命が奪われてしまいます。
誰もが安心してペットと暮らし、もしもの時には新しい飼い主さんに引き継げる仕組み作りが大切です。
この記事では、愛するペットの未来を守るためにできる対策や備えについて解説します。
ペットのための負担付遺贈

遺贈とは、遺言に基づいて財産の全部または一部を無償で譲渡することです。
負担付遺贈は、条件をつけた上で遺贈をします。
ペットのための負担付遺贈では、「ペットのお世話をすること」を条件として、財産の全部または一部を譲渡することができます。
遺贈で財産を受け取る対象は、個人・法人・団体でも構いません。
ペットのお世話を頼める知人がいない場合には、終生飼養を有料で行なう団体に委託することも可能です。
遺贈の注意点は、相続放棄の恐れがあることです。
遺贈は遺言書による一方的なものなので、自由に放棄することができてしまいます。
負担付遺贈で新しい飼い主さんにペットのお世話を依頼する時は、必ず事前に了承を得ておきましょう。
また、遺留分について十分に考慮する必要があります。
遺留分とは、民法で定められた「法定相続人が最低限保証される相続財産の割合」です。
亡くなった方の子や親がいる場合に、問題となることが多いです。
ペットのための負担付死因贈与契約

死因贈与とは、あげる人ともらう人の合意による贈与契約によって、死亡を原因として財産の全部または一部を譲渡することです。
負担付死因贈与契約は、条件をつけた上で贈与をします。
ペットのための負担付死因贈与契約では、「ペットのお世話をすること」を条件として、財産の全部または一部を譲渡することができます。
負担付死因贈与契約は双方の合意に基づく契約によるため、負担付遺贈のように相続放棄されることはありません。
しかし、財産だけ受け取ってペットのお世話を放棄されたとしても、チェックする仕組みがないため多くの不安があります。
また、負担付死因贈与契約をする場合も、遺留分に十分注意しましょう。
ペットのための信託契約

負担付遺贈や負担付死因贈与契約のデメリットを補えるのが信託契約です。
相当の手間やお金がかかりますが、きちんとした信託契約を結べば、確実にペットの命を守ることができます。
信託には複数の役割の人や団体が登場し、互いにチェックし合いながら協力して行います。
登場するメンバーと役割は以下の通りです。
1.飼い主(委託者・受益者)

中心となるのは、もちろん飼い主さんです。
ペットを守るために望ましい飼育方法や財産の管理について意思を明確にしていきます。
信託契約に必要な費用は飼い主さんが負担します。
新しい飼い主さんを探すのも飼い主さんの役割です。
元気にペットと暮らしている間は、当初受益者になります。
2.財産を管理する人(受託者)

信託契約に基づき、財産を管理する人や団体のことです。
ペットのお世話に必要な費用を支出するための責任を負います。
飼い主さんにお子さんが複数いる場合、1人が財産管理人になり、別の子が新しい飼い主になることもできます。
3.新しい飼い主(受益者)

契約によって、飼い主さんが亡くなる前から新しい飼い主さんにペットを譲渡することもできます。
入院や老人ホームへの入所、認知症のリスクに備えて、契約書の内容を考えることが大切です。
新しい飼い主さんは、元の飼い主さんの希望に従ってペットのお世話をし、その費用を受託者から受け取ります。
ペットの健康な生活と幸せを守るため、信託契約書には「ペットの名前・種類・健康状態・希望する医療・特定のお世話など」を具体的に記載しておきましょう。
4.見張り役(監督人)

飼い主さんがお世話をできなくなった後に、受託者(財産の管理人)と受益者(新しい飼い主)を監督する見張り役が必要です。
見張り役は、信託が適切に行われているかをチェックします。
行政書士などの士業者に依頼することもできます。
5.法的アドバイザー(専門家)

信託契約書の作成や手続きは、非常に複雑で専門的な知識がかかせません。
法的なアドバイザーは、適切な形で信託が設定されるようにサポートする立場です。
ペットのための信託は、まだ新しい制度です。
そのため、相続の専門家であっても、ペットへの知識が浅いと適切に対応できない場合があります。
ペットが家族であるという認識を共有でき、ペットのための信託に詳しい専門家を選ぶことが重要です。
契約書と遺言書は公正証書で作成する

現状では、ペットの命を守るためには信託契約がもっとも安心です。
信託契約とは別に、遺言書も作成しておくと良いでしょう。
遺言書にペットに対する想いや信託に関わる人への感謝を記載しておけば、ペットのための財産が信託として残されていることが相続人や遺言執行人に伝わります。
契約書や遺言書は、公正証書として作成するのがおすすめです。
信託だけでなく遺贈や死因贈与契約も同様です。
公正証書は証拠力が高く、無効になる恐れがほぼありません。
公正証書遺言のメリットや作成方法については、以下の関連記事をご参照ください。
<関連記事>
【まとめ】遺言書・契約書の相談は専門家へ!
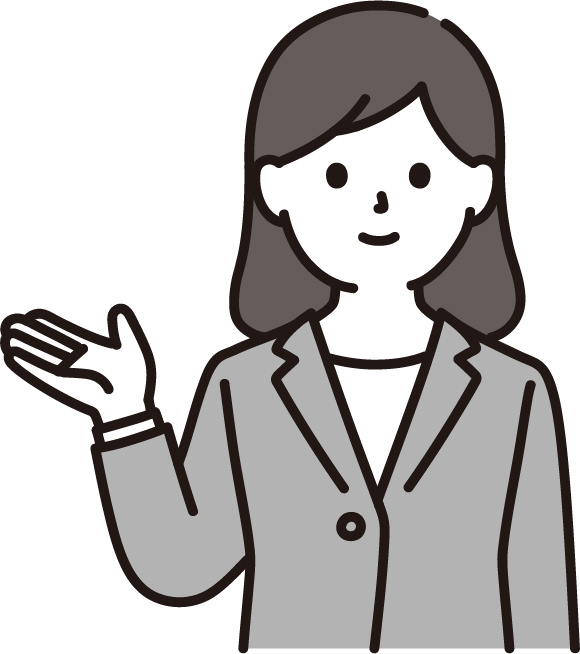
大切な家族であるペットの命や幸せな生活を守るには生前対策が重要です。
法律に詳しいだけでなく、ペットを家族としてみなす考え方に理解のある専門家を選びましょう。
当事務所は飼い主さんの想いに寄り添い、希望を実現できるよう「ペットのための信託契約・負担付遺贈・負担付死因贈与契約」をトータルでサポートいたします。
まずは、お気軽にお問合せください。
詳しくはコチラからご確認できます。

