高齢者が安心して猫と暮らせる「永年預かり制度」とは?

「もう年だから、猫とは暮らせない」
そう考えて、猫との暮らしを我慢しているご高齢者も多いようです。
しかし、人生のほとんどを猫と暮らしてきた方にとって、猫のいない生活はとても寂しいでしょう。
この記事では、ご高齢者の孤独を癒し、保護猫譲渡の助けとなる「永年預かり制度」をご紹介します。
永年預かり制度とは

「永年預かり制度」とは、特定非営利活動法人 猫と人を繋ぐツキネコ北海道から始まった制度です。
保護猫を「譲渡する」のではなく、「貸す」という形をとります。
年齢や健康上の理由で猫との暮らしを諦めていた方が利用できます。
広く里親さんを募集できるので、「愛護団体・猫と暮らしたい人・保護猫」の3者にとって嬉しい制度です。
永年預かり制度のメリット

永年預かり制度は、通常の保護猫の譲渡とは異なり、あくまで猫を「貸す」という形です。
そのシステムには、社会問題を解決するメリットがいくつもあります。
高齢者が猫と暮らせる
ほとんどの保護猫団体では、60歳や65歳をボーダーラインとして譲渡の制限をしています。
理由は、病気などが原因でご高齢の飼い主さんが猫のお世話をできなくなることを懸念するからです。
しかし、「永年預かり制度」を利用すれば、何歳の方でも猫と暮らし始めることができます。
健康状態には個人差があり、年齢だけで判断できるものではありません。
実際に、保護猫を返却する方は少なく、看取りまでお世話できる方が多いそうです。
もしもの時に助かる

元気な方でも、いつ病気やケガをするかわかりません。
ご高齢の場合は、なおさらです。
もしも飼い主さんが入院したり死去したりすると、猫のお世話がストップしてしまいます。
ゴハンや水がもらえずトイレも汚いままでは、猫は生きていけません。
しかし、「永年預かり制度」を利用すれば、もしもの時に愛護団体が猫のお世話をしてくれるので安心です。
保護猫の譲渡が促進される

超高齢化社会において、保護猫の譲渡を年齢で制限していては、なかなか譲渡が進みません。
愛護団体のシェルターや個人のボランティア宅は、保護猫でいっぱいになってしまいます。
猫は単独で生活する動物なので、たくさんの猫と生活スペースを共有するとストレスがたまりがちです。
「永年預かり制度」を利用すると、1匹だけで暮らすことができます。
永年預かり制度の注意点

永年預かり制度はとても有益な制度ですが、その利用には注意点もあります。
メリットだけでなく注意点も理解した上で、利用しましょう。
猫が限定されることもある
「永年預かり制度」の対象となる猫は、シニア猫や病気のある猫に限定されていることがあります。
猫の平均年齢は約15歳で、20歳を超えることも多いため、子猫は対象外ということが多いでしょう。
しかし、愛護団体によっては、どんな保護猫でもOKというところもあります。
まずは、自宅近くの愛護団体のHPを見て、実際に足を運んでみるのがおすすめです。
見守りが必要

もしもの時に助かる「永年預かり制度」ですが、ご高齢者が倒れた時、すぐに気づける体制が必要です。
愛護団体が見守りしてくれる場合もありますが、こまめに連絡を取り合うことは期待できません。
友人や親せきに「永年預かり制度」を利用していることを伝えておきましょう。
何かあった場合に、愛護団体にすぐ知らせてもらうようにしておくことが大切です。
永年預かり制度の利用方法

まずは、インターネットなどで情報を集めましょう。
検索窓に「猫 永年預かり制度 ○○県」と入力するのがおすすめです。
「永年預かり制度」を利用できる愛護団体を探し、問い合わせをします。
保護猫との面会予約をして、愛護団体を訪問しましょう。
「永年預かり制度」対象の中から猫を選びます。
好きなゴハンや治療の有無などの情報を教えてもらいましょう。
自宅で必要な物の準備をし、保護猫を届けてもらって猫との暮らしがスタートです。
愛護団体の定めたルールで連絡を取り合うこともありますが、何もなければ連絡する必要がないことも多いです。
もしも健康上の問題が生じたら、早めに愛護団体と連絡を取りましょう。
引き取りのタイミングについて、一緒に計画を立てることができます。
【まとめ】永年預かり制度で生活に彩りを!
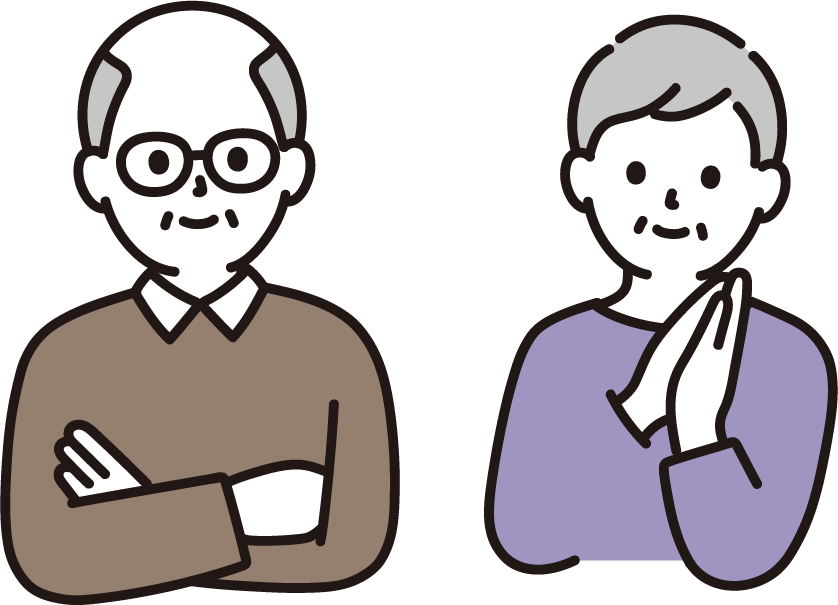
猫との暮らしは、生活に彩りを与えてくれます。
猫は散歩が必要なくマイペースに過ごすことが多いので、ゆったりと暮らしたいご高齢者にはピッタリですね。
年齢を理由に猫との暮らしを諦めていた責任感と愛情あふれるご高齢者こそ、本来なら猫との暮らしに向いていると言えます。
「永年預かり制度」を利用すれば、社会課題解決の一助にもなり、毎日が楽しくなるでしょう。
愛猫のための生前対策を行いたい方は、コチラもご覧ください。

