高齢者が猫と暮らすメリットと注意点とは?

「猫を飼うなら保護猫を」という風潮が一般的になってきました。
しかし、「60歳以上の方には譲渡しない」という保護団体も多いようです。
譲渡を断られると、どうしても猫が飼いたいご高齢者は、ペットショップで子猫を購入してしまいます。
そして、入院や入所のタイミングで愛猫を手放すという悲しい結末が増えています。
シニア世代がペットと暮らすのは、無理なのでしょうか?
仕事や子育てから解放され、いざ人生を満喫しようという時に、パートナーや家族と疎遠になっている方も多くいらっしゃいます。
傍らに猫がいれば、生活にハリが出るばかりでなく、生きる目的にもなるでしょう。
この記事では、ご高齢者が猫と暮らすメリットと注意点を解説します。
行政や民間のサポートを利用し、計画的に生前対策を行えば、ご高齢者でも猫と暮らすことができます。
ご高齢者が猫といつまでも元気に楽しく暮らせる方法を考えるきっかけとなれば幸いです。
高齢者が猫と暮らすメリット

年齢に関わらず、大好きな猫と暮らすと、幸福度や人生の満足度がアップします。
ご高齢者は、健康の促進や生きがいの創出にもつながるでしょう。
運動量が増える
猫と暮らすと、フードや水を与えたりブラッシングをしたりするお世話が必要になります。
また、部屋の掃除に加えて、猫のトイレ掃除もしなければいけません。
活発な猫の場合、オモチャで遊びたがるでしょう。
猫のお世話は、たくさんあります。
やらなければいけないことがあると、運動量が増えます。
シニア世代は運動不足になりがちですが、猫と暮らすと健康が促進されるでしょう。
会話が増えて寂しくない

猫は会話ができませんが、一緒に暮らす人の言葉を理解しているように思えるから不思議です。
毎日、自然と猫に話しかけるようになるでしょう。
猫がいれば、1人暮らしでも寂しくありません。
家族がいる場合には、猫に関する話がふくらみ、家庭内の会話が増えます。
夫婦間でも、猫を子どものように感じて日々の会話が生まれやすくなります。
会話のキャッチボールがあると、脳への刺激にもなるでしょう。
認知症対策としても、猫を介して会話が増えることは有益です。
他者との交流が生まれる

犬と暮らすと、散歩の際に他の飼い主さんと会話を交わすことも多いようです。
猫の場合は家から出ないですし、鳴き声や走り回る音も小さいため、ご近所に気づかれないこともあるでしょう。
しかし、今はSNSなどで、同じ趣味を持つ人と簡単に交流できます。
スマホやパソコンを使う高齢者は、使わない高齢者と比べて幸福度が高いという調査があります。
猫に関する動画や写真を発信する人も多く、コメントなどで交流すると楽しいでしょう。
高齢者が猫と暮らす注意点

年齢を重ねると、生活の中でさまざまな困りごとが増えていきます。
猫と暮らすと、経済的にも身体的にも負担がかかるので注意しましょう。
お金がかかる

猫を飼育するには、フードやトイレ砂などの日常的な出費が必要です。
病気やケガをした際には医療費がかかり、1回の診察で数万円を支払う時もあります。
経済的余裕がない場合には、猫と暮らしていけるかを考えてから飼い始めましょう。
旅行に行きにくくなる
定年退職後にゆっくり旅行を楽しみたいと考えている方も多いですね。
しかし、猫と暮らすと、2泊3日以上の旅行はしづらくなります。
もし、旅行を頻繁にしたいのであれば、猫を飼育しない方が良いのではないでしょうか。
お互いの寿命を考える

人生100年時代とは言いますが、健康寿命は男女ともに70代です。
猫の寿命はどんどん伸びており、現在は約15歳ですが、20年以上生きる猫も増えています。
猫と飼い主さんの寿命を考えた上で、子猫ではなく成猫やシニア猫を迎え入れることを検討しましょう。
ペットショップには子猫しかいませんが、保護団体や行政の施設では成猫の譲渡が行われています。
ご高齢者には、子猫よりも成猫がおすすめです。
終の住処を選ぶ

ご高齢の飼い主さんが老人ホームや病院に入った場合、猫を最後までお世話できなくなります。
代わりに猫のお世話をしてくれる人を探しておきましょう。
ご自身より10歳以上若い人が安心です。
親戚や知人に預けられない場合は、老猫ホームや保護団体と契約をして終生飼養や里親さんへの譲渡をお願いしましょう。
猫と一緒に入れる老人ホームもあります。
元気なうちから情報収集をして、愛猫のために終の住処を選ぶのがおすすめです。
遺言書を作成する

日本の法律では、猫に遺産をのこすことができません。
そのため、もしもの時に備えて新しい飼い主さんを選び、飼育費用を渡す契約をしておくと安心です。
猫のために財産を用意するには、遺贈・贈与契約・民事信託などが利用できます。
専門家にご相談の上、公正証書を作成するのがおすすめです。
<関連記事>
【まとめ】遺言書で愛猫を守ろう!
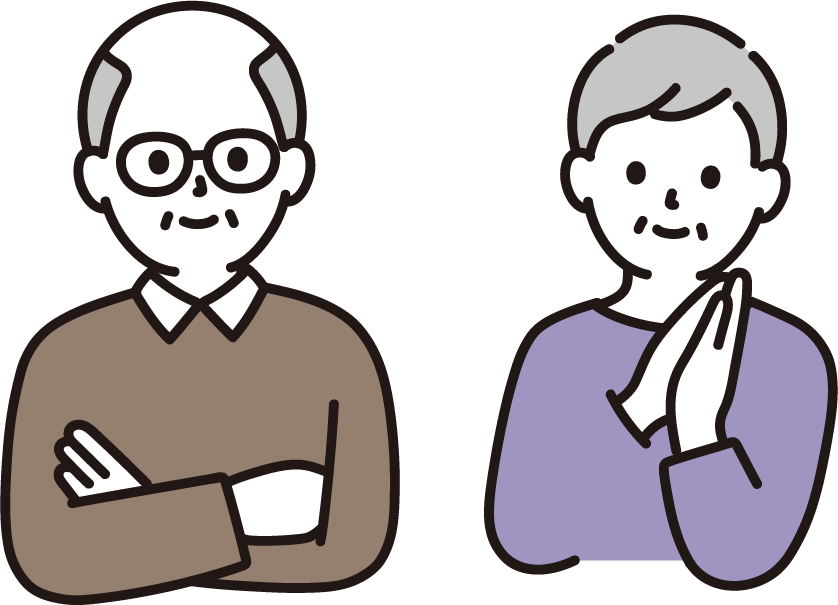
ご高齢者が猫と暮らすためには、もしもの備えが不可欠です。
新しい飼い主さんを探しておき、飼育費用をのこす準備をしましょう。
遺言書や契約書を公正証書として作成しておくことで、飼い主さん亡き後、愛猫のために財産を使ってもらうことができます。
愛猫の看取りまで飼い主さんが元気でいられたら、それはとても幸せなことですね。
当事務所では、遺言書や契約書の作成をトータルでサポートします。
まずはお気軽にお問合せください。
詳しくはコチラからご確認できます。

