パートナーシップ制度と同性カップルの4つの相続対策

「このまま同性同士の結婚が認めらなかったら、わたしの遺産はどうなるのだろう。」
そのような疑問を持ち、不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
現在の日本では、長く連れ添っていても相続権が得られないなど、同性カップルには厳しい状況です。
しかし、少しずつではありますが権利を守るしくみができつつあります。
この記事では、「パートナーシップ制度」と同性パートナーがいる場合にできる4つの相続対策について解説します。
生前対策をしっかりと行えば、同性のパートナーにご自身の財産を遺すことが可能です!
パートナーシップ制度とは
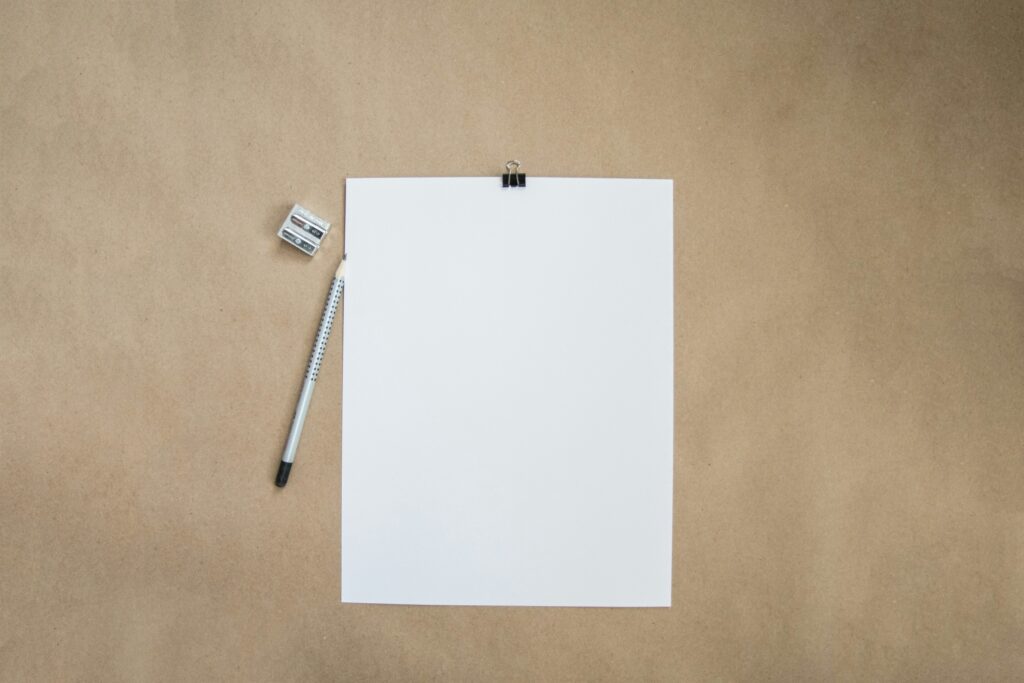
「パートナーシップ制度」とは、同性カップルが法的に結婚できない日本において、地方自治体が独自に2人の関係を結婚に相当する関係であると認め、証明書を発行する制度です。
東京都渋谷区から始まり、2023年時点で328自治体まで広がっています。
人口カバー率は70%を超え、地方自治体レベルでは公的な認定を受けることができるようになってきました。
パートナーシップ制度のメリット

この制度により、同性カップルは以下のようなメリットを享受できます。
- 公営住宅への入居
- 病院での面会や手術の同意
- 民間の保険や金融サービスなどの利用
しかし、パートナーシップ制度は「同性婚制度」とは異なるため、自治体が法律の範囲を超えて法的効果を定めることはできません。
とはいえ、同性婚が制度化されていない現状において、各自治体のパートナーシップ制度はもっとも有効な制度と言えるでしょう。
パートナーシップ制度の条件
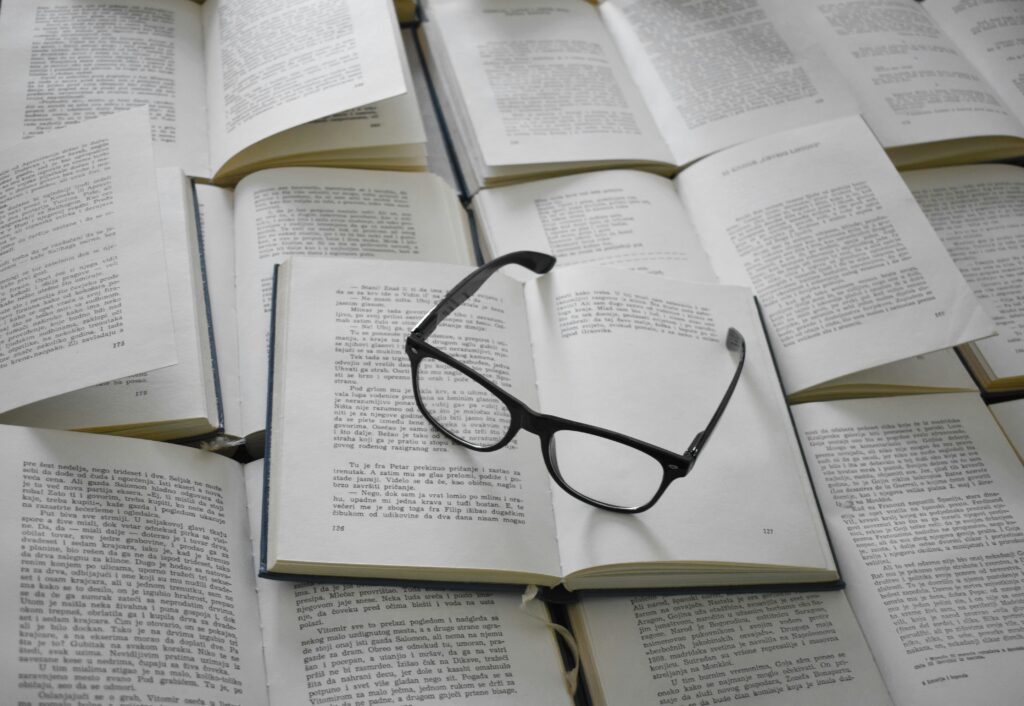
各自治体によって受けられるサービスが異なりますが、共通して以下の条件が設けられています。
①当事者がパートナーシップ関係を有すること
②当事者双方が18歳以上であること
③当事者双方が相手以外の者と婚姻又はパートナー関係にないこと
④当事者双方が相手方と近親関係にないこと
⑤当事者双方又は一方が制度の適用を受けようとする地方公共団体に住民登録を有し又は居住していること
成人要件・非婚等要件・非近親者要件は、原則的に民法上の婚姻の成立要件と同じものです。
パートナーシップ制度の手続き

パートナーシップ制度は、各自治体が独自に制定するものです。
パートナーシップ宣誓の手続きは、自治体によって異なります。
ここでは、いくつかの自治体における手続き方法をまとめました。
- 事前予約: 多くの自治体では、宣誓日の事前予約が必要です。(電話・FAX・メール・来所)
- 必要書類の準備: 戸籍謄本・住民票・本人確認書類など必要な書類を準備します。
- 宣誓: 予約した日時に2人そろって指定場所へ行き、宣誓書を提出します。
- 内容確認: 提出した書類の内容確認が行われます。
- 受領カード等の交付: 宣誓後、受領カードなどの証明書が交付されます。
東京都のようにオンラインで手続きできる自治体もあります。
連携協定とファミリーシップ制度

制度利用者がその自治体から転居する場合は、改めて転入先で手続きをする必要があります。
他市町村に引っ越しをするたびに手続きをするのは、けっこうな手間です。
このような負担を軽減するため、一部の自治体では連携協定の動きが進んでいます。
また、同性カップルという2者間を対象とするパートナーシップ制度だけでなく、子どもや親を含めたファミリーシップ制度を導入する自治体も増えてきました。
子どもの学校や病院での手続きにおいて、家族としての証明をすることが期待できます。
制度の効果や手続きの流れを把握するのは大変ですし、行政窓口での対応に不安を覚える方もいらっしゃるでしょう。
行政書士は、手続きのサポートや窓口への同行もできます。
パートナーシップ制度やファミリーシップ制度を利用すれば、公的な認定を受けることができるため生活がしやすくなります。
手続きに関して分からないことや困ったことがあれば、当事務所にお気軽にお問合せください。
同性カップルができる4つの相続対策

同性カップルは婚姻関係にありませんので、残念ながらお互いの相続人になることができません。
財産をのこす方法としては、内縁(事実婚)のカップルと似たような対策をとることになります。
1. 遺言書による遺贈を行う
遺言書を作成し、パートナーに遺贈する旨を記載することで、同性のパートナーにも財産をのこすことができます。
遺贈とは、遺言によって相続財産を渡すことです。
相続人以外に財産をのこす方法としては、もっとも一般的と言えます。
遺贈を受ける時には、相続税がかかることに注意が必要です。
遺言を作成する時は、遺留分を侵害しないように気をつけましょう。
遺留分とは、民法で定められた「最低限の財産を受け取る相続の割合」です。
パートナーに、親・法律上の妻・子がいる場合に問題となります。
遺言を作成するなら、公正証書遺言をおすすめします。
2. 死因贈与契約をする

死因贈与とは、贈与者と受贈者との間で結ばれる贈与契約です。
贈与者の死亡によって効力が生じる契約のことを指します。
死因贈与は、お互いの合意によって行う契約であるという点で、一方的な意思に基づく遺言とは異なります。
死因贈与は、口頭でも行うことができます。
しかし、トラブルになることが予想されますので、必ず「死因贈与契約書」を作成するようにしましょう。
死因贈与契約書は、公正証書として作成する方が安心です。
死因贈与も遺留分侵害額請求権の対象となります。
遺留分を侵害しないように気をつけましょう。
ちなみに、贈与税ではなく、相続税がかかります。
3. 生命保険の受取人にする

同性のパートナーを生命保険の受取人にするという方法もあります。
一般的には、生命保険の受取人は配偶者または2親等以内の親族です。
従来の生命保険では、同性のパートナーが保険金の受取人になることはできませんでした。
しかし、各自治体でパートナーシップ制度が広がってきたことによって、同性のパートナーを受取人として指定できる保険会社が増えています。
条件は保険会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
同性のパートナーが受け取った保険金は、相続税の対象となります。
また、契約者を同性のパートナー、被保険者を本人、保険料の支払いは同性のパートナーとする方法もあります。
その際、本人がパートナーに毎年110万円の非課税枠内で贈与をし、そこから保険料を支払うと、結果的に財産を渡しているのと同じことになります。
被保険者である本人が死亡し、同性のパートナーが受け取った保険金には所得税がかかることに注意が必要です。
4.養子縁組をする
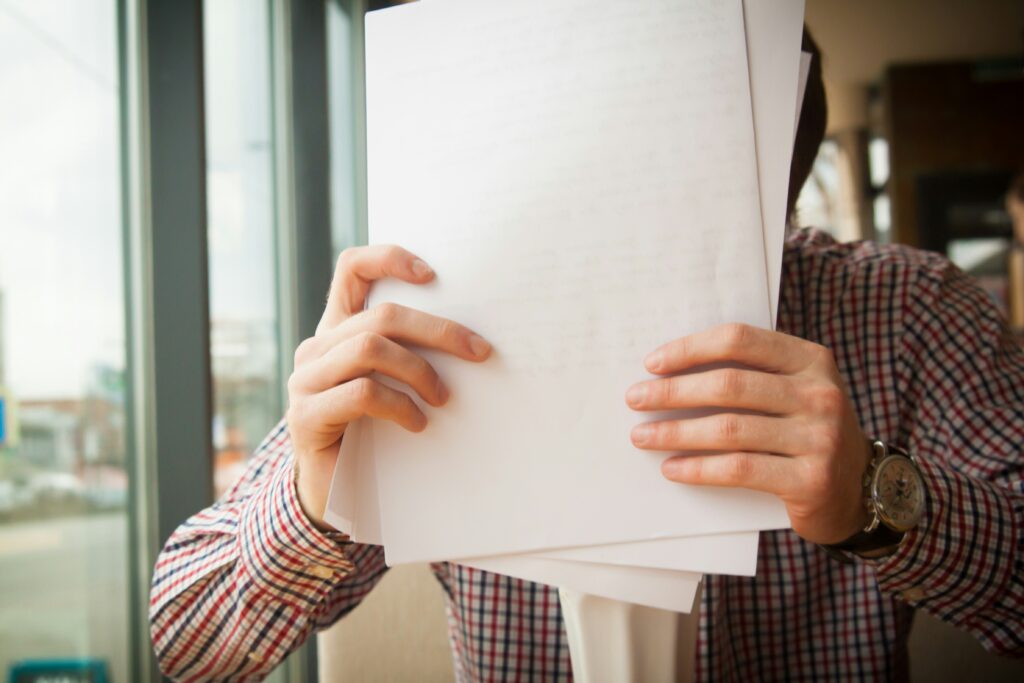
現在の日本では、戸籍法上の問題で、同性同士では婚姻届を受理してもらうことはできません。
しかし、養子縁組をすることで、同じ戸籍に入ることができます。
養子縁組とは、血のつながらない者同士を親子とする制度のことです。
パートナーと親子関係になることに違和感がある方も少なくないでしょう。
しかし、養子縁組をすることで、相続が発生したときにはお互いに相続人になることができます。
その際には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続されるので注意が必要です。
また、養子縁組をしてしまうと、パートナーシップ制度を利用できなくなるデメリットもあるため、どちらが良いか検討する必要があります。
【まとめ】同性パートナーの生前対策は公正証書で
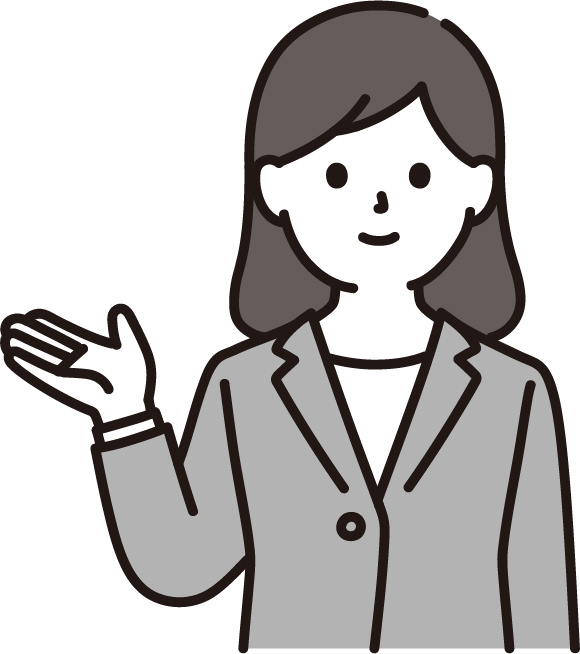
現在の日本では、同性カップルは婚姻することが認められていないため、相続権がありません。
しかし、生前対策をしっかり行えば、財産を大切なパートナーにのこすことができます。
費用や手間がかかりますが、遺留分を考慮した上で遺言書や契約書を公正証書にすることで、想いを確実に実現できます。
公正証書のメリットについては、コチラの記事もお読みください。
行政書士は公正証書作成のサポートができます。
行政窓口への同行も可能ですので、お気軽にお問合せください。
詳しくはコチラでご確認できます。

