内縁のパートナーに遺産をのこす4つの方法

長年連れ添ったり、2人の間に子どもがいたりしても、婚姻届けを出していない場合、法律上は夫婦と認められません。
住民票を同じくして「夫(未届)」「妻(未届)」とすることによって、事実婚を証明することはできますが、それでも内縁のパートナーには相続権がありません。
しかし、生前対策を行うことにより、内縁のパートナーにも財産をのこすことができます!
大切な存在である内縁のパートナーに財産を残す4つの方法を解説します。
1. 生前贈与を行う

生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。
法定相続人だけでなく、誰にでも生前贈与することができます。
生前贈与を受ける時は、贈与税がかかることに注意が必要です。
贈与には、年間110万円の基礎控除額があります。
贈与税を支払わないようにするためには、基礎控除額を考慮しましょう。
2. 遺言書による遺贈を行う

遺言書を作成し、内縁のパートナーに財産を遺贈する旨を記載することで意思を実現できます。
遺贈とは、遺言者の死亡によって相続財産を渡すことです。
相続人以外に財産をのこす方法としては、もっとも一般的と言えます。
遺贈を受ける時は、相続税がかかることに注意が必要です。
内縁のパートナーの場合、配偶者控除等の税の軽減対策が適用されないだけでなく、相続税が2割増しになります。
また、遺言を作成する時は、遺留分を侵害しないように気をつけましょう。
遺留分とは、民法で定められた「最低限の財産を受け取る相続の割合」です。
親や法律上の妻、子がいる場合に問題となります。
3. 特別縁故者の手続きをする
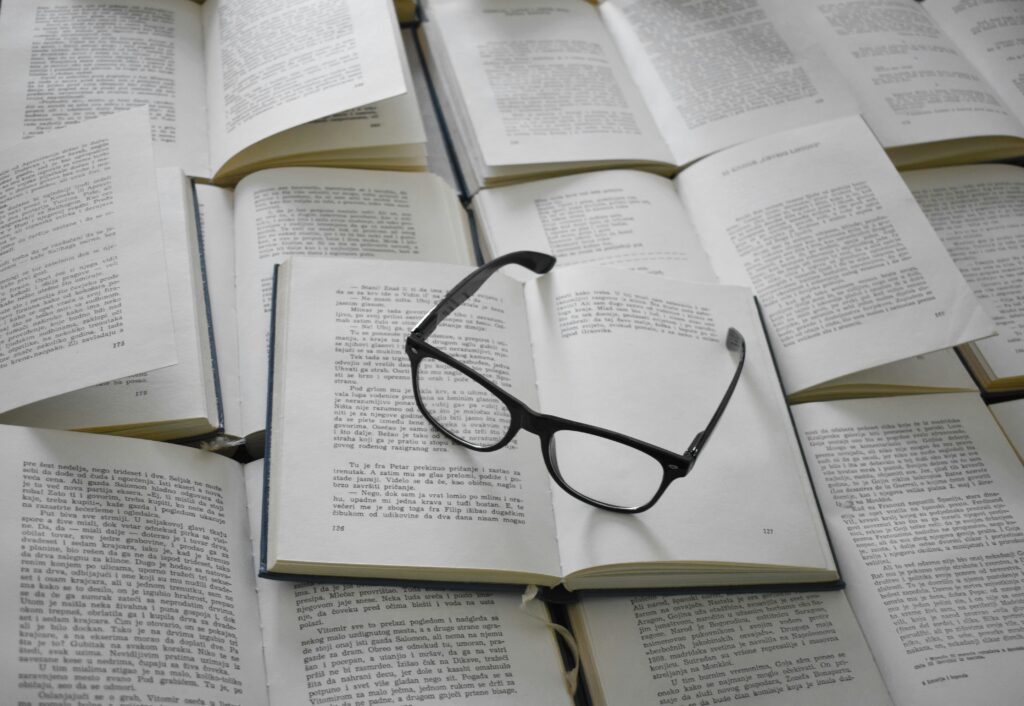
家庭裁判所で「特別縁故者の申し立て」を行って認められると、内縁関係でも相続財産分与で財産を受け取ることができます。
特別縁故者とは、亡くなった被相続人と特別な関係にあった人です。
生計を共にしていたり、対価なしに亡くなった人の身の回りのお世話をしていたりすると認められます。
内縁のパートナーは、その条件を満たすケースが多いため、特別縁故者に認められやすいです。
ただし、特別縁故者が財産を分与されるのは、法定相続人が誰もいない場合に限られます。
また、受け取れる財産は家庭裁判所が決定した額になり、相続税がかかることにも注意が必要です。
4. 生命保険の受取人にする

内縁のパートナーを生命保険の受取人にするという方法もあります。
一般的には、生命保険の受取人は、配偶者または2親等以内の親族です。
しかし、生命保険会社によっては、以下の条件を満たせば、内縁のパートナーでも認められる場合があります。
- お互いに戸籍上の配偶者がいない
- 保険会社の所定期間に同居している
- 保険会社の所定期間に生計を共にしている
条件は保険会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
内縁のパートナーが受け取った保険金は、相続税の対象となります。
本人(被保険者)がパートナー(契約者・受取人)に毎年110万円の非課税枠内で贈与をし、そこから保険料を支払う方法もあります。
結果的に財産を渡しているのと同じことになります。
ただし、被保険者である本人が死亡し、内縁のパートナーが受け取った保険金には所得税がかかることに注意が必要です。
内縁のパートナーが遺産を受け取る時の注意点

相続においては、法律上の婚姻関係にあるかないかで大きく立場が変わります。
そのため、内縁のパートナーが遺産を受け取る時は、内縁の関係にあったことを証明できるようにしておくことが重要です。
内縁関係を証明するには、以下のような方法があります。
- 住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載する
- パートナーシップ合意契約書(事実婚に関する契約書)を作成する
- 自治体のパートナーシップ証明制度を利用する
【まとめ】内縁関係でも財産をのこせます
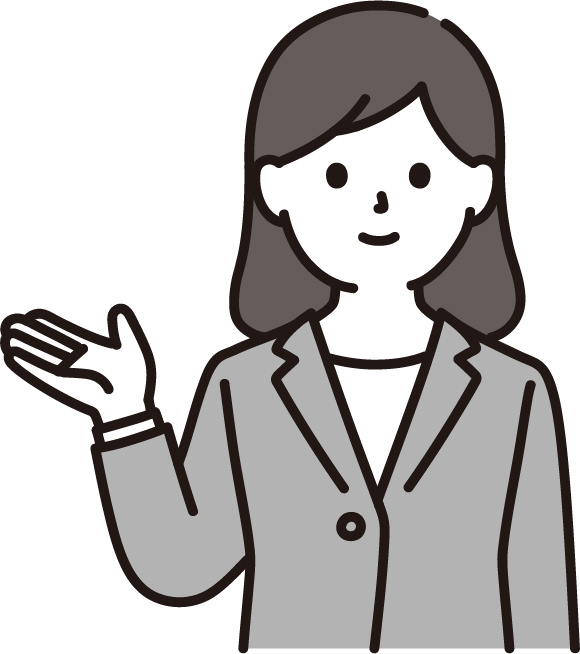
内縁のパートナーに財産をのこすには、相続や贈与のルールを理解し、生前に準備することが欠かせません。
遺言を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言を作成すれば、形式不備によって無効になる心配がありません。
公正証書をおすすめする理由は、コチラの記事をぜひお読みください。
当事務所では、公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。
まずはお気軽にお問合せください。
詳しくはコチラからご確認できます。

