遺贈寄附とは?メリットと注意点を解説します

「いい人生だった」
「たくさんお金を稼いで良かった」
そう思えるための選択肢の1つが遺贈寄附です。
人生のエンディングを迎える準備を進める中で、さまざまな不安や後悔が出てくるかもしれません。
残りの人生をより豊かにするために、遺贈寄附について学んでみませんか?
遺贈寄附とは

遺贈寄附とは、財産を特定の団体や機関に寄附する遺贈の方法です。
寄付先は、国・地方公共団体・公益法人・NPO法人・学校法人・国立大学法人などです。
近年、社会貢献の手段として注目を集めています。
遺言書や信託などにより、生前に自分の意思を遺しておく必要があります。
遺贈寄附によって、次世代を担う人や社会に貢献することが可能です。
遺贈との違い

遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲与することです。
法定相続人(子や配偶者等)や法定相続人以外の第三者または法人へ不動産や金銭を遺贈することができます。
遺贈寄附は公益団体等へ相続財産を譲与することにより、その団体の活動を支え、社会的課題の解決や社会貢献につなげます。
寄附との違い

寄附も遺贈寄附も、公益的な活動をする団体等に対して財産を無償で提供することは同じです。
一般的な寄附は「現在」、遺贈寄附は「自分が死亡した時」に寄附する点が大きく異なります。
寄附には、募金・義援金・クラウドファンディングなどが含まれます。
資金に余裕のある大金持ちを除けば、毎日の生活費が必要な一般の人にとって多額の寄附はなかなかできません。
しかし、生きているうちは多額の寄附ができなくても、ご自身が亡くなった時に遺贈寄付するのであれば、大きな金額を寄附しても困ることはないでしょう。
亡くなった後に財産をゼロにできる遺贈寄附は、注目を集めています。
遺贈寄附のメリット

遺贈寄附には多くのメリットがありますが、おもに以下の2つです。
社会貢献ができる
遺贈寄附の最大のメリットは、社会貢献ができることでしょう。
遺言がなければ、遺産はすべて法定相続人に渡ります。
相続人のいない方の遺産は国庫に入ります。
しかし、遺贈寄附をすれば、財産の使い道を自分で選ぶことが可能です。
お世話になった学校や地域社会に恩返しすることができ、被災地や医療支援活動などにも活用できます。
税制上の優遇がある
遺贈寄附する分の遺産は、相続税の対象外です。
相続税は個人を対象としている税金なので、法人に遺贈寄附した場合には相続税がかかりません。
また、寄附金控除については、被相続人(亡くなった人)の所得から控除されます。
死亡から4ヶ月以内に、相続人が所轄税務署へ準確定申告をします。
遺贈寄附の方法

遺贈寄附には、大きく分けて2つの方法があります。
生前に自分で準備をする場合
もっとも代表的なのは、遺言書を作成する方法です。
財産の全部または一部を公益団体等に寄附することを遺言で残します。
死因贈与契約、生命保険や信託による寄附もあります。
相続人が遺贈寄附する場合
手紙・エンディングノート・口頭などで相続人に遺贈寄附の意思を伝えておき、実行してもらう方法です。
遺言書とは異なり、手紙やエンディングノートには法的効力がないことに注意しましょう。
遺族(喪主)が香典返しに代えて、遺贈寄附をすることもあります。
相続人が相続財産を受け取ってから寄附しますので、原則として相続税の対象となります。
しかし、相続開始から10ヶ月以内に税制優遇団体へ寄附して相続税申告すれば、相続税計算の対象から外すことが可能です。
また、税制優遇団体への寄附であれば、寄附金控除の適用を受けることができます。
遺贈寄附の注意点

遺贈寄附をする際は、以下の3点に注意しましょう。
遺留分に配慮する
遺贈寄附をする時は、まず家族や相続人のことを第一に考えましょう。
遺言では遺留分を侵害しない財産配分とし、残された家族や相続人との生前の関係や心情などにも十分配慮してください。
遺留分とは、「亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産の割合」です。
また、家族や相続人が遺贈寄附を知って驚かせないようにしておくことが重要です。
生前のうちに、遺贈寄付する意思があることを伝えおきましょう。
専門家に相談する

遺贈には、相続に関する知識や遺言書の作成が必要となります。
専門家に相談するとスムーズです。
また、寄付する相手(団体)の事情にも配慮することが大切です。
特に不動産を寄附したい場合には、事前に寄附先の団体や専門家を通じて確認しましょう。
寄附を受ける団体も、あらゆる財産や条件で遺贈寄附を受けられる訳ではありません。
遺言執行者を決めておく

遺贈寄附を確実に実行するために、遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行者とは、「遺言書の内容に基づいて相続手続きを進める人」です。
遺言書で遺言執行者を指定しておくことができます。
遺言執行者には法律の知識や手続きの経験が必要となるため、遺言作成をサポートした専門家がそのまま遺言執行者になることも多いです。
遺言執行者は強い権限を持ち、遺贈寄附に不満を持つ相続人がいても、遺言の内容を実現させることを使命とします。
【まとめ】遺贈寄附は専門家へご相談を!
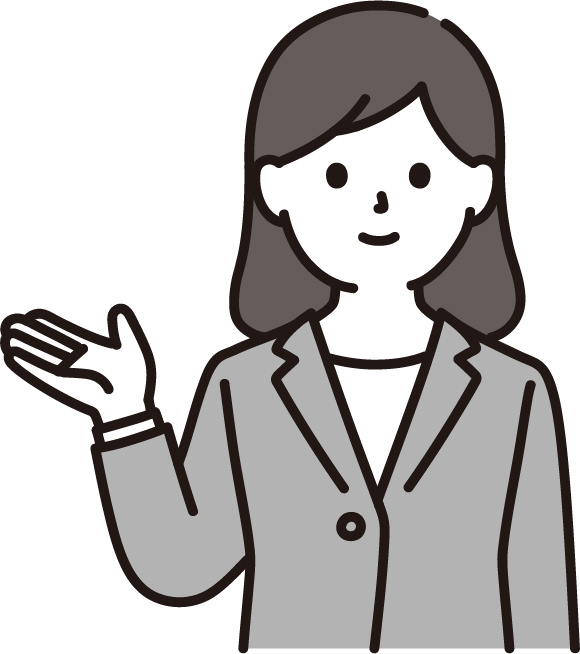
遺贈寄附と聞くと、多額の寄附を想像されるかもしれません。
しかし、数万円でも社会貢献になりますし、築き上げた大切な財産の行き先をご自身で決めることで満足感を得られます。
遺贈寄附には、法律の知識が必要です。
せっかく遺言書を作成しても無効になったり、遺留分の争いが起きてしまったりとトラブルが発生する可能性があります。
遺贈寄附をする際は、専門家にご相談するのがおすすめです。
当事務所では、遺贈寄附に際して遺言書の作成をトータルでサポートします。
詳しくはコチラをご確認ください。

