40代でも始めるべき!遺言書で家族を守れる理由とは

40代で遺言書を作成すべき5つの理由

1. 想定外のリスクへの備え
人生には想定外のリスクが付きものです。
40代は、仕事や家庭で大きな責任を担う世代でありながら、突然の事故や病気などの予測できない出来事が起こる可能性もあります。
遺言書を作成することで、こうした不測の事態に備え、自身が望む財産分配や家族の将来を明確にしておくことが可能です。
「備えあれば憂いなし」という言葉の通り、遺言書は家族に対する思いやりの形でもあります。
2. 家庭や財産を持つ年代
40代は家庭を持つ人も多く、住まい・貯蓄・保険などの財産を築き、大切な家族との関係が人生の中心となりやすい時期です。
このような背景から、遺言書を通じて財産分配を明確にしておくことで、残された家族が無用な混乱や争いを避けられるよう備えることが求められます。
また、遺言書があれば、子どもや配偶者の生活を守るための具体的な指針を示すことができます。
3. 早めの準備が与える安心感
遺言書を早い段階で準備しておくことは、精神的な安心感を与えてくれます。
40代で遺言書を作成すると、万が一の際にも自身の意向が確実に反映されるため、心の余裕を持って日々を過ごすことができます。
遺言書作成は「死」を意識するというよりも、むしろ家族や将来を守るための「生」に関する計画です。
早めに取り組むことで、家族全体に安心が生まれます。
4. 法定相続トラブルの回避
法定相続では、相続人が複数いる場合にトラブルが起こりやすくなる傾向があります。
例えば、兄弟間の意見が食い違った場合や財産の分け方について話がまとまらない場合などが挙げられます。
遺言書を作成しておけば、法定相続に従った場合の分配と異なる意思を記すことが可能です。
その結果、相続トラブルを未然に防ぎ、家族間の良好な関係を維持することが期待できます。
5. 健康リスクが徐々に高まる時期
40代は、体力が衰え始め、健康面でのリスクが徐々に増加する年代です。
ストレスや生活習慣の影響で病気のリスクが高まると言われています。
万が一の事態に備えるためにも、遺言書を準備しておくことが重要です。
近年は健康リスクに対する意識も高まり「まだ若いから大丈夫」という考え方を改め、早い段階での遺言書作成が推奨されています。
遺言書を用意することは、家族に信頼と安心を残す大切なステップです。
遺言書の基本的な種類と特徴

種類ごとの適したケースとは
普通の形式の遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、簡便さが求められる場合や費用を抑えたい方に適しています。
一方、公正証書遺言は、法的トラブルを避けたい場合や大きな財産を持つ場合に適しています。
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に選ばれる形式です。
40代という将来を見据えた時期には、自身の財産や家庭状況に適した形式を選ぶことが重要です。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、遺言者が紙に自ら手書きで作成します。
大きなメリットは、費用を抑えられる点です。
40代のように家庭や財産を持ち始めた時期に、気軽に作成しやすいでしょう。
しかし、形式や内容に不備があると無効となることに注意が必要です。
全文・氏名・日付を手書きで記入し、押印する必要があります。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成します。
メリットは、法的に有効な書類を確実に作成できる点です。
形式不備や内容の検討が万全なので、法定相続トラブルを未然に防げます。
作成には公証役場への相談と証人2名の立ち合いが必要です。
費用がかかる点がデメリットですが、40代のうちにしっかり準備しておくことで、将来の安心感を得られます。
遺言書の保管
自筆証書遺言を作成するなら、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用するのがおすすめです。
この制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、遺言書の安全な保管が可能になります。
3,900円と手頃な費用で遺言書が管理されるため、家族にとっても安心です。
40代で初めて遺言書を作成する際には、この制度を利用して安全に保管することを検討しましょう。
また、公正証書遺言は公証役場で安全に管理されます。
公正証書遺言および法務局で保管した自筆証書遺言は、検認が不要です。
遺言書が家族に与える4つのメリット

1. 家族間の争いを防ぐ効果
遺言書を作成することで、財産分配の方向性を明確にすることができます。
これにより、相続に関する意見の食い違いを防ぎ、家族間の争いを未然に回避することが可能です。
40代で作成する遺言書は、将来的な相続トラブルを避けるための重要な準備といえます。
明確な遺言書があることで、家族全員が公平感を持ち、円満な相続を実現できます。
2. 未成年の子への財産配分
40代は、未成年の子がいる家庭が多いです。
子は年齢に関係なく、財産を承継することができます。
しかし、未成年者は法律行為ができないため、遺産分割協議では代理人による同意が必要です。
遺産分割協議において、親権者(父や母)は代理人になれません。
裁判所に特別代理人を選んでもらいますが、それには手間がかかります。
遺言書があれば、未成年の子どもがいても、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。
3. 配偶者・相続人の負担軽減
遺言書がない場合、相続手続きには相当な時間と労力を要することがあります。
一方、遺言書があれば、負担が軽減され、配偶者や相続人が心的・実務的なストレスから解放されます。
4. 特定の人への感謝を形に
遺言書を用いることで、特定の人に対して感謝の意を込めた財産の分配を行うことができます。
法定相続だけでは伝えられない個別の想いを形にできるのも、遺言書の大きなメリットです。
例えば、長年お世話になった人への贈与や、特に感謝している家族への配分など、故人の意思を具体的に反映させることが可能です。
40代で遺言書を準備することで、感謝の想いを早めに記しておける点も大きな魅力です。
遺言書作成時に気をつける4つのポイント

1. 形式不備の防止
遺言書を作成する際には、形式不備を防ぐことが最も重要です。
自筆証書遺言の場合、全文・氏名・作成日付を手書きし、忘れずに押印する必要があります。
これを怠ると、遺言書全体が無効になります。
また、遺言内容が曖昧であった場合、相続人間のトラブルが生じやすいため、内容を明確かつ簡潔に記載しましょう。
専門的な用語や判断に迷う場合は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。
2. 遺留分への対策
遺言書を作成する際は、遺留分を考慮する必要があります。
遺留分とは、配偶者・子供・直系尊属に対して法律で保証された最低限の財産割合のことです。
この遺留分の権利を侵害するような遺言を作成してしまうと、相続人間で遺留分侵害額請求が行われ、トラブルに発展する可能性があります。
特に、相続人以外の第三者に多くの財産を渡すような遺言内容にする場合は、遺留分を考慮した上で明確な計画を立てることが重要です。
3. 家族構成や財産状況に応じた内容
遺言書は、家族構成や財産状況に応じて作成することが重要です。
例えば、未成年の子がいる場合には、財産をどのように管理するかを具体的に記載しておくと良いでしょう。
また、共有名義の不動産やデジタル資産など、扱いがやや複雑な財産についても細かく記載しておくことで、相続時の負担を軽減することができます。
40代は一般的に家庭や財産が充実し始める世代ですので、現在の状況に合った内容を盛り込みながら、将来的な変更も考慮した柔軟な記載が求められます。
4. 遺言内容の変更
遺言書は、1度作成すれば終わりではありません。
40代で作成した遺言書は、その後の家族構成や財産状況の変化に応じて定期的に見直すことが推奨されます。
新たな財産を取得したり、家族が増減したりした場合には、内容を変更しましょう。
遺言書を更新する際は、古い方の遺言を明確に取り消すとともに、新たな遺言書を適正な形式で作成することが大切です。
また、公正証書遺言の場合、専門家への相談を再度行うことで、最新の法律に基づいた遺言を確実に作成することができます。
遺言書を作成するための4つのステップ

1. 自分の財産の整理・把握
遺言書を作成する際には、まず自分が保有する全ての財産を整理し、正確に把握することが重要です。
現金や不動産だけでなく、株式や保険の契約内容、さらにはデジタル資産(ネット銀行口座や仮想通貨など)も含めてリストアップしましょう。
この作業を行うことで、家族への遺産分配をより具体的かつスムーズに進めることができます。
40代の方は家庭や財産が安定し始める時期ですので、早めにこのステップを実行することが将来のトラブルを回避する一助となります。
2. 相続人の範囲の確認
次に、自分の財産を相続する権利を持つ相続人の範囲を確認する必要があります。
配偶者や子どもがいれば法的に優先される相続権があり、場合によっては直系尊属(親)も相続人となります。
なお、兄弟姉妹は遺留分がありませんので、全体的なバランスを考慮した配分を検討することが大切です。
こうした確認作業は遺言書の内容に直結するため、正確に把握しておきましょう。
3. 信頼できる専門家への相談
遺言書は法律に基づいて作成されるため、形式や内容に不備があると無効になってしまうリスクがあります。
そのため、行政書士・司法書士・弁護士・税理士といった信頼できる専門家への相談をおすすめします。
遺産分配の複雑さや相続人間での争いを防ぐためにも、専門家のアドバイスを受けることで、適切な遺言書を作成できます。
40代で遺言書作成を検討する際は、人生設計や家庭の状況に理解のある専門家を選ぶとより安心です。
4. 完成した遺言書の保管
遺言書が完成した後は、その保管方法を慎重に考える必要があります。
現在、自筆証書遺言については法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用することで、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。
この制度を利用しない場合でも、信頼できる人に預けたり、安全な場所に保管するようにしましょう。
また、公正証書遺言を選ぶ場合は、公証役場に原本が保管されるため、特に紛失やトラブルの心配が少なくなります。
適切な保管方法を選択することで、遺言書の効力を確実に保つことができます。
【まとめ】遺言書作成は専門家へ!
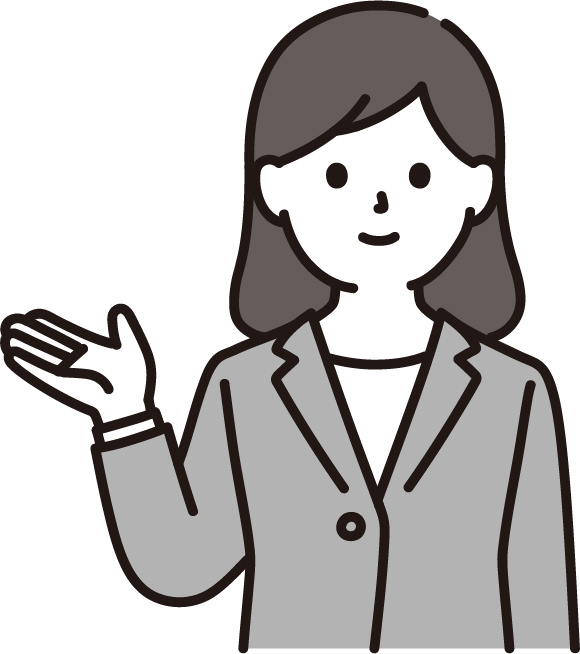
40代は公私ともに忙しく、責任も大きな年代です。
長期的な安心感を得られるため、早めに遺言書を作成することをおすすめします。
家族構成や財産内容に変更が生じた場合には、何度でも遺言書を作り変えることができます。
遺言書の作成には法的な知識が欠かせません。
専門家に相談することでスムーズに作成することが可能です。
当事務所では、遺言書作成をトータルでサポートします。
詳しくはコチラをご確認ください。

