自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?

遺言には、「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」の3種類があります。
そのうち、秘密証書遺言はあまり利用されていません。
もっとも手軽に作成できるのは自筆証書遺言ですが、より確実に遺言の内容を実現できるのは公正証書遺言です。
この記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを説明します。
自筆証書遺言の作成・保管

自筆証書遺言は、遺言者本人が紙に遺言内容の全文を手書きします。
日付と名前を書き、署名の下に押印します。
添付する財産目録は、パソコンで作成しても構いません。
銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付することも認められています。
遺言内容の本文は、必ず手書きにしないと無効になるため注意しましょう。
自筆証書遺言は遺言者が自宅で保管するほか、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます。
公正証書遺言の特徴

自筆証書遺言と公正証書遺言を比較すると、公正証書遺言の特徴が見えてきます。
公正証書遺言には7つの特徴があります。
1.ほとんど無効にならない
公正証書遺言は、公証人によって作成されます。
有効な形式で確実に作成されるため、無効となる心配がありません。
自筆証書遺言は、方式不備で無効になったり、内容によっては紛争の元になったりします。
2.字が書けなくても作成できる
自筆証書遺言は、遺言の内容すべてを手書きにする必要があります。
手が不自由な場合には作成することができません。
しかし、公正証書遺言は、署名以外は公証人が作成します。
もし、署名も書けない場合でも、公証人の職印で代替することが可能です。

3.高度な証明力がある
自筆証書遺言は、遺言者本人だけで作成できます。
手軽ですが、厳格な形式に合っていない場合には無効になります。
一方、公正証書遺言は、公証人のほかに2名の証人の立会いも必要です。
遺言者の真意が確認され、手続きが適正に行われたことが保証されます。
4.検認手続きがいらない
自筆証書遺言は、自筆証書遺言保管制度を利用した場合をのぞき、検認手続きが必要です。
遺言者が亡くなった後、遺言書を発見した人が家庭裁判所に持参して検認手続きを受けなければいけません。
一方、公正証書遺言は、検認不要なので、すぐに相続手続きが開始できます。
相続人等の負担が少なくなります。

5.安全に保管され出張も可
自筆証書遺言を自宅で保管していた場合、紛失や破損の恐れがあり、発見者による隠ぺいや改ざんの可能性もあります。
自筆証書遺言保管制度を利用すれば、それらの心配はなくなりますが、遺言者本人が法務局に持参しなければいけません。
外出や移動が難しい場合には、自筆証書遺言保管制度は利用しづらいでしょう。
一方、公正証書遺言は遺言者が病気等で動けない場合でも、公証人が出張して作成してくれます。
自宅だけでなく、老人ホームや病院にも出張可能です。
6.費用がかかる
費用に関しては、自筆証書遺言の方が安上がりです。
しかし、紙・ペン・印鑑さえあれば作成できるので手軽ですが、形式不備などで無効になると意味がありません。
費用をかけてでも、公正証書遺言を作成する方が安心でしょう。
公正証書遺言は、公証人手数料が政令で定められています。
財産が多くなるほど、公証人手数料も高くなります。
ちなみに、公証人への相談は無料です。

7.遺言書の写しが入手できる
自筆証書遺言は、保管制度を利用した場合には写しが手元に残りません。
遺言者が亡くなったら、相続人等が遺言の証明書の交付を請求することになります。
遺言者の出生から死亡までの戸籍等の謄本一式等を添付して、遺言情報証明書の交付を申請します。
その後、交付された遺言情報証明書を用いて相続手続きを行います。
一方、公正証書遺言は、作成した時に遺言書の正本1通と謄本1通を受け取るのが通常です。
遺言者の死後に、あらためて交付を請求する必要がありません。
遺言者の公正証書遺言が見つからない時は、遺言検索ができます。
その結果、遺言を保管している公証役場がわかれば、郵送で謄本の請求が可能なので足を運ぶ手間がありません。
【まとめ】公正証書遺言の作成は専門家へ
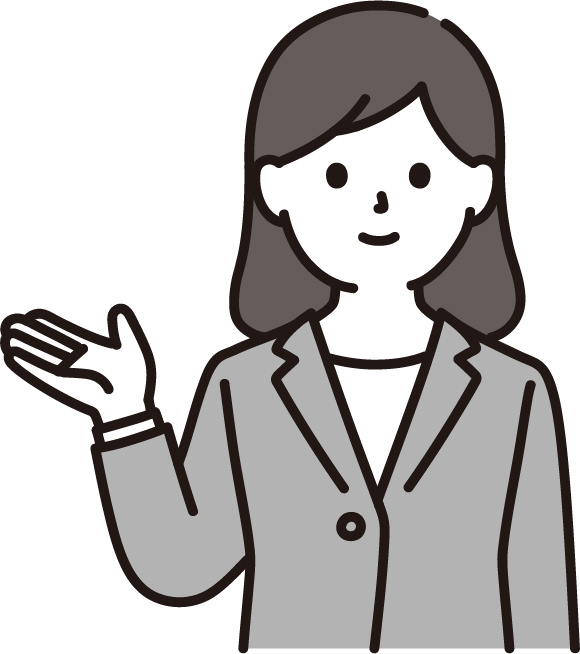
手軽な自筆証書遺言と比べ、公正証書遺言は費用と手間がかかります。
しかし、無効になる恐れがない点が大きなメリットです。
当事務所では、公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。
まずはお気軽にお問合せください。
詳しくはコチラでご確認できます。

