自筆遺言証書保管制度とは?保管方法やメリット・注意点
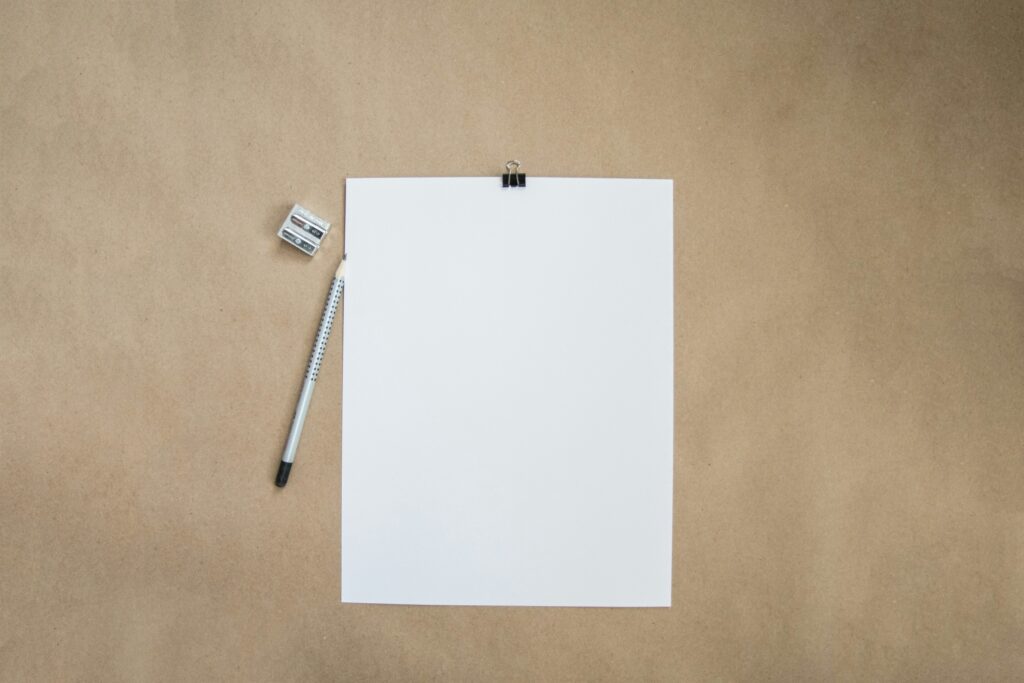
遺言は、ご自身亡き後に「財産を誰にどれくらい渡すか」という意思表示です。
想いを記し、実現するための手段と言えます。
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
もっとも気軽に作成できるのは、自筆証書遺言です。
しかし、自筆証書遺言は、形式不備で無効になる恐れや紛失・隠ぺい・偽造などの可能性があります。
それらのデメリットを補う方法として、自筆遺言証書保管制度が作られました。
この記事では、自筆遺言証書保管制度について、保管方法・メリット・注意点を解説します。
自筆遺言証書保管制度とは

自筆証書遺言は、遺言者本人が「遺言の全文・日付・氏名」を手書きし、押印することによって作成します。
証人は不要で、ペン・紙・印鑑さえあれば自分1人で作成することが可能です。
費用もかかりません。
しかし、形式が決まっており、一定の要件を満たさないと無効になる恐れがあります。
また、せっかく遺言書を書いても死後に発見されなかったり、検認の手間がかかったりします。
自筆証書遺言の欠点を補うため、2020年7月から、自筆遺言証書とその画像データを法務局で保管できる制度が始まっています。
この保管制度は、全国312カ所の法務局で利用できます。
保存期間は、遺言者死亡から原本は50年間、画像データは150年間です。
注意すべき点は、ご自身が法務局に足を運び、遺言書の保管手続きをする必要があることです。
病気やケガなどで移動ができない場合には、自筆証書遺言保管制度は利用できません。
法務局での申請手続きは、事前予約制です。
予約サイト・電話・窓口で必ず予約するようにしてください。
申請書は法務省のHPからダウンロードでき、窓口でもらうこともできます。
自筆証書遺言と申請書の他に、本人確認書類(免許証など)・住民票の写し等(本籍と戸籍の筆頭者の記載があるもの)・3,900円の収入印紙(遺言書保管手数料)が必要です。
自筆証書遺言保管制度のメリット

より多くの人に遺言書を作成してもらい、スムーズに相続手続きをして欲しいという国の願いがあり、自筆証書遺言保管制度が作られました。
自筆証書遺言保管制度には、以下のメリットがあります。
適切に保管できる
自筆証書遺言は自宅で保管できますが、遺言書の紛失・盗難・偽造・改ざんの心配があります。
自筆証書遺言保管制度を利用して、法務局で遺言書の原本とその画像データを保管すれば安心です。
遺言書の存在が確実に守られます。
無効な遺言書になりにくい
自筆証書遺言を保管する際には、民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局職員が確認するため、外形的なチェックが受けられます。
ただし、遺言書の内容について有効性を保証するものではなく、作成時に相談にのってもらうことはできない点に注意が必要です。

相続人に発見してもらいやすくなる
遺言者が亡くなった際には、指定した人へ遺言書が法務局に保管されていることが通知されます(3名まで)。
この通知は、遺言者があらかじめ希望した場合に限り実施されるものです。
法務局が、遺言者の死亡の事実を確認した時に通知されます。
通知制度によって、遺言書が発見されないことを防げます。
検認手続が不要になる
自宅で自筆証書遺言を保管している場合、遺言者が亡くなった後には家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
検認は、偽造や改ざんを防ぐためです。
検認を受けなければ、遺言書に基づく不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。
しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認が不要です。
そのため、相続人等が速やかに遺言書の内容を実行できます。
自筆証書遺言保管制度の注意点
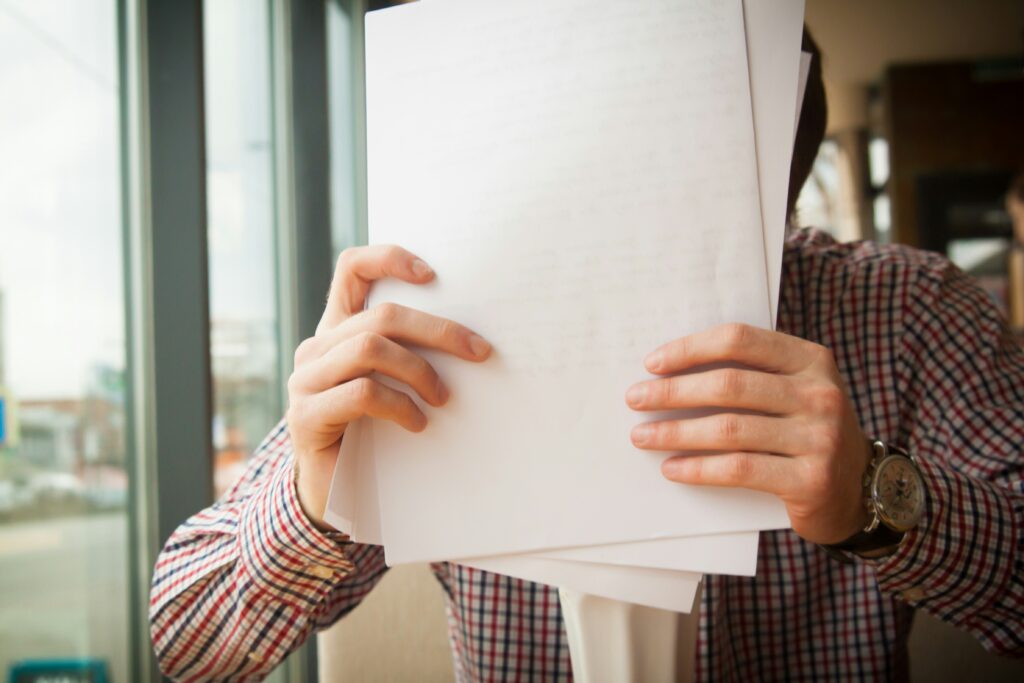
以下のように様式がきちんと決まっているので、確認の上で作成する必要があります。
- 用紙はA4サイズ(裏面には何も記載しない)
- 余白を確保する(上側5ミリメートル・下側10ミリメートル・左側20ミリメートル・右側5ミリメートル)
- 遺言書本文・財産目録には各ページに通し番号でページ番号を記載する
- 複数ページでも綴じ合わせない
様式を守らないと、保管してもらえませんので注意しましょう。
【まとめ】専門家のアドバイスがおすすめ!
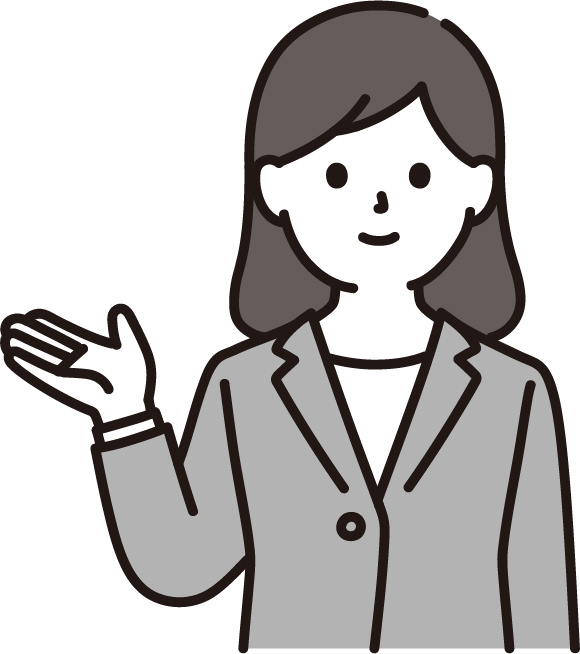
費用をかけずに気軽に作成できる自筆証書遺言は、法務局での保管制度によって、さらに利用しやすくなりました。
しかし、作成方法を間違えると、有効に意思を残せないばかりか争いの元になる可能性もあります。
確実に意思を実現するためには、専門家の力を借りるのがおすすめです。
当事務所は、自筆証書遺言の作成をトータルでサポートします。
まずはお気軽にお問合せください。
詳しくはコチラからご確認できます。

