親に「遺言書を書いて」と言いにくい!角を立てずに伝える実践ガイド

この記事のポイント
- 言いにくさの正体は「お金が欲しいと聞こえる」「縁起でもない」「距離が近い」の3つ。
- 伝え方は〈ニュースきっかけ〉〈私が心配なんだ〉〈思い出から入る〉の3パターンが有効。
- 遺言書は「取り分の話」より「残された人を守る準備」。言わないままのほうが負担が大きい。
はじめに:親子は近いからこそ、言いにくい

子どものころに言われた「勉強しなさい」「早く寝なさい」。
大人になったら「結婚は?」「子どもは?」。
・・・言われる側はイラっとするし、「ほっといて、私の人生だから」と心の中で反論もします。でも親は本気で心配なんですよね。
やがて立場は静かに入れ替わります。
今度は私たちが「病院行ってる?」「転ばないでね」と声をかける側に。そして、その延長線上の「最難関テーマ」がこれです。
「お母さん(お父さん)、遺言書って用意してある?」
分かってはいるけれど、口に出すのは難しい。この記事は、その「言いにくさ」をほぐし、角を立てずに伝える具体的な言い方までまとめた実践ガイドです。
なぜこんなに言いにくいのか(3つの理由)
- お金目当てに聞こえそう
「誰がいくら」だけの話に受け取られやすい不安。 - 縁起でもないと言われそう
「まだ元気なのに、もうその話?」と感情が動きやすい。 - 距離が近いからこその難しさ
親は大切な人。傷つけたくない思いがブレーキになる。
まずは「言いにくいのは当然」と認めること。そこからがスタートです。
実は言わないままのほうが大変になる
大切な話題を避け続けると、いざという時に・・・
- 銀行や不動産など手続きが止まる
- 兄弟やパートナー間で言った言わないの争いが起きる
- いちばんつらい時期(喪失直後)に実務判断を迫られる
遺言書は「取り分の交渉」ではなく、悲しみの負担を増やさないための思いやりです。
角が立ちにくい伝え方:3つの入り口

① ニュース・きっかけ方式
「この前ニュースで見たんだけど、遺言書がないと手続きがすごく大変になることがあるんだって。うちも準備を考えたほうが安心かなと思って。」
第三者の話題から入ると、責めていない姿勢が伝わりやすい。
② 私が心配なんだ方式
「もし何かあった時に、私が慌てないようにしたいの。お母さん(お父さん)の考えを、メモで残しておいてもらえると私が助かる。」
「取り分を聞きたい」ではなく、自分の不安の整理としてお願いする形。
③ お金ではなく思いから
「この指輪はお姉ちゃんに、この道具は弟に、みたいな形見の希望ってある? それを書いておいてもらえると、私たちケンカしないで済むから助かる。」
金額ではなく想いの引き継ぎから始めると、会話が柔らかくなる。
NGになりやすい言い方 → 言い換え例
- ×「遺産どうするの?」
→ ○「手続きで困らないように、考えを書いておいてもらえると助かる」 - ×「早く遺言書を書いて」
→ ○「時間のある時に一緒に整理してみない?」 - ×「全部私がもらうでしょ?」
→ ○「誰に何を残したいか、お母さん(お父さん)の気持ちを先に聞かせて」
どのタイミング・どんな場がいい?
- 落ち着いた日常(記念日や法要の直前直後は避ける)
- 横並びの場(車内・散歩・キッチンなど向かい合いすぎない)
- 時間制限あり(15〜20分で一度切る。続きはまた今度でOK)
まず何を書き残すと助かる?ミニ・チェックリスト
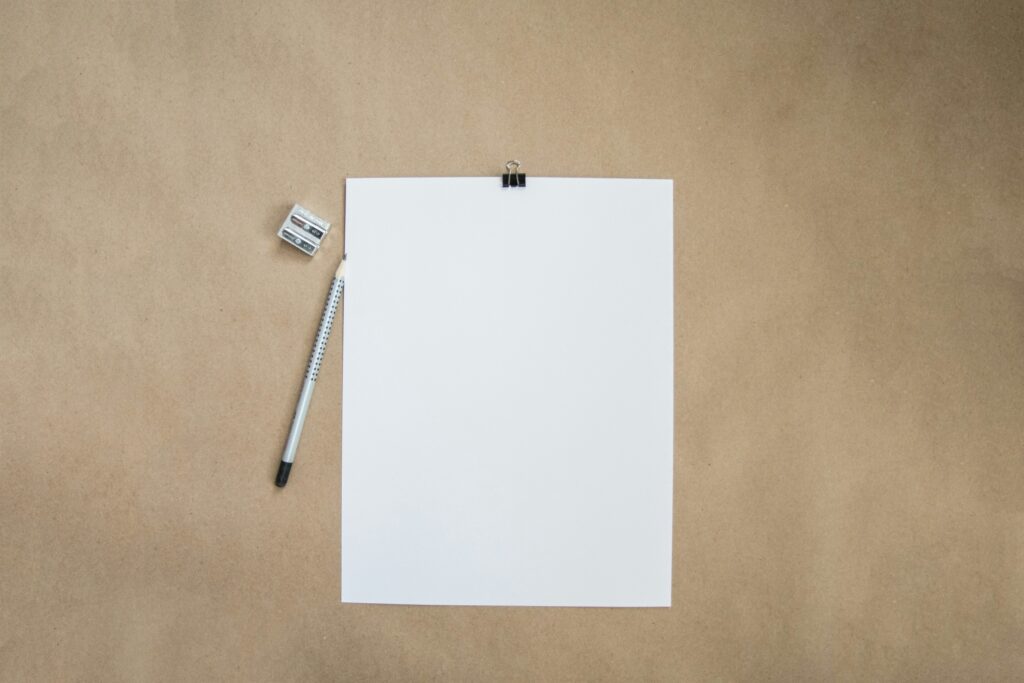
- 連絡してほしい人リスト(電話・メール)
- 金融機関の一覧(支店名まで。暗証番号は書かない)
- 住まい・不動産のメモ(登記簿・管理会社)
- 思い出の品のゆくえ(誰に渡したいか)
- ペットの世話人と費用の考え(フードや病院の情報)
- デジタルのこと(有料サービス、写真の保管場所など)
- もしもの医療・介護の希望(延命、最期の場所 など)
※この「希望メモ」を足がかりにして、最終的には遺言書(自筆・公正証書)へ昇格させるのが理想です。
会話が前に進んだら:次の一歩
- 希望メモをいっしょに作る
- 家族の構成・財産の大まかな一覧を、ざっくり書き出す
- 保管先と見直し時期(1〜2年に一度)を決める
- 公正証書遺言など正式な形への移行を検討
【まとめ】大切なのはお金の話ではなく思いやりの仕組み
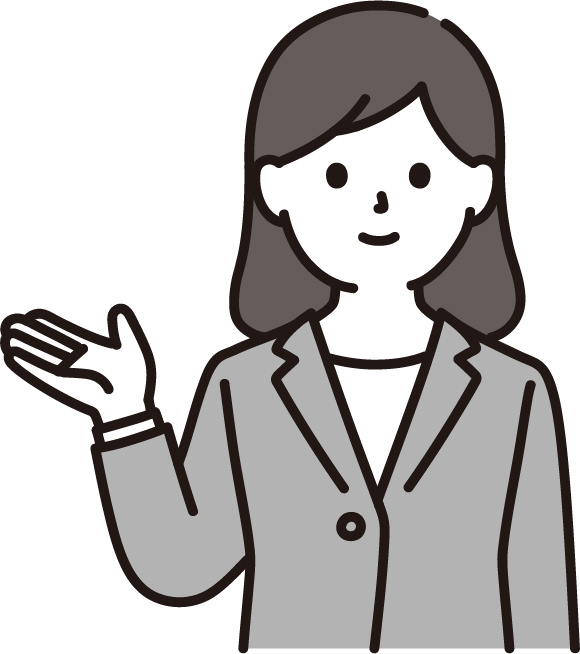
「遺言書を書いて」は、相手の寿命を心配する言葉ではありません。
残される人が、余計に傷つかないための小さな準備です。
まずは、言いやすい一文をスマホのメモに。
- 「ニュースで見たんだけど、手続きが大変になることがあるって」
- 「私が慌てないように、考えを少し残しておいてほしい」
- 「思い出の品、誰に渡したいか決めてある?」
その一歩が、十分にやさしい始まりになります。
当事務所では、遺言書の作成をトータルでサポートしています。
まずは相談から、小さな一歩を始めてみませんか?
詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。

