相続人がいても遺贈寄付できる?トラブル回避のポイント

近年、「自分の遺産を社会の役に立てたい」と考える方が増え、亡くなった後に財産を寄付する「遺贈寄付」が注目を集めています。
動物愛護団体や医療支援、環境保全など、自分の想いを未来につなぐ方法として選ばれています。
しかし、こんな心配をされる方も少なくありません。
「うちには相続人がいるから、遺贈寄付は難しいのでは?」
この記事では、相続人がいる場合でも遺贈寄付を行うことができるのか、そしてトラブルを防ぐために何に気をつければよいのかを行政書士の視点からわかりやすく解説します。
遺贈寄付とは?

まずは「遺贈寄付」の基本から押さえておきましょう。
遺贈とは、遺言によってご自身の財産の一部または全部を相続人以外の特定の個人や団体に譲ることをいいます。
そして、その相手がNPO法人や財団などの公益団体である場合、「遺贈寄付」と呼ばれます。
遺贈には主に2つの方法があります。
- 包括遺贈:全財産または一定の割合を寄付する
- 特定遺贈:○○団体に100万円、不動産の一部など特定のものを寄付する
特定遺贈の方が遺族とのトラブルになりにくいと言われています。
相続人がいると遺贈寄付はできないの?

結論から言えば、相続人がいても遺贈寄付は可能です。
ただし、「遺留分(いりゅうぶん)」に注意する必要があります。
遺留分とは、配偶者や子どもなどの法定相続人に認められた最低限の取り分のこと。
例えば、遺言で「すべての財産を○○団体に寄付する」としても、遺留分を侵害している場合、相続人から寄付の取り消し(遺留分侵害額請求)を求められる可能性があります。
つまり、寄付そのものは自由ですが、相続人の権利にも配慮する必要があるということです。
相続トラブルを防ぐための3つのポイント

1. 遺留分を侵害しないようにする
相続人のうち、配偶者・子・直系尊属(父母など)には遺留分が認められています。
この遺留分を超えて寄付してしまうと、後からトラブルになる可能性が高まります。
事前に遺留分を計算し、それを侵害しない範囲で寄付額を決めることが大切です。
2. 公正証書遺言で明確に意思を残す
せっかくの遺贈寄付も、遺言書の内容が不明確だったり、形式に不備があったりすると無効になることがあります。
おすすめは「公正証書遺言」を作成することです。
公証役場で公証人が作成してくれるため、形式的なミスがなく、信頼性が高いのが特徴です。
寄付先の正式名称や寄付する財産の内容を明確に記載しましょう。
3. 事前に家族に想いを伝えておく
遺言書にすべてを託すのも1つの方法ですが、最も大切なのは「家族との対話」です。
遺贈寄付をしたい理由・自分の想い・社会とのつながり等について家族にきちんと伝えておくことで、感情的な反発や誤解を避けることができます。
「エンディングノート」に寄付への想いを記しておくのもおすすめです。
寄付先選びの注意点

遺贈寄付は、寄付先の選び方も大切です。
信頼できる団体かどうか、以下のポイントを確認しましょう。
- 法人格があるか(NPO法人・公益財団法人など)
- 活動内容や理念が自分の意思に合っているか
- 遺贈寄付を受け入れる体制があるか(事前相談の可否)
- 寄付の使途が明確になっているか
また、団体によっては不動産のような管理が難しい資産を受け取らない場合もあります。
事前に寄付先へ確認することが非常に重要です。
行政書士に相談するメリット

遺贈寄付を円滑に進めるには、遺言書作成や相続の専門家である行政書士のサポートが役立ちます。
- 相続人の有無や遺留分の確認
- 法的に有効な遺言書の作成
- 寄付先団体との事前調整 など
第三者の立場から、家族と寄付先の間をつなぐ調整役としてもお手伝いできます。
想いをかたちにする第一歩として、ぜひご相談ください。
【まとめ】遺贈寄付は「準備」と「配慮」で実現できる
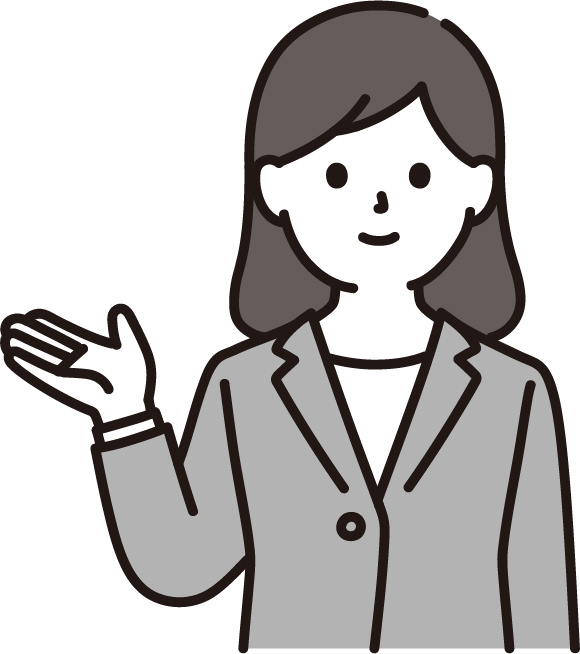
相続人がいても、遺贈寄付をあきらめる必要はありません。
大切なのは、以下のポイントです。
- 相続人の遺留分に配慮すること
- 意思を法的に明確に残すこと
- 家族との対話を大切にすること
あなたの大切な財産を未来の社会につなぐために、遺贈寄付はその想いを形にする方法です。
当事務所では、遺言書作成を通して、あなたの「最後の社会貢献」をしっかりサポートいたします。
詳しくは行政書士ようこオフィスのホームページでご確認ください。

