人は「遺言書を書く人」と「書かない人」の2つに分けられる!あなたはどっち?

「人は2つに分かれる。それは遺言書を書く人と書かない人だ。」
少しドキッとする言い方ですが、50代の今こそ落ち着いて考えるいいタイミングです。
親のこと、子どもの独立、住まいとお金、これからの暮らし。
遺言書は「最後の宣言」というより、家族へのメモと段取り表のようなものです。
完璧な決断を1度で出す必要はありません。
まずは資産と気持ちを軽く整理して、将来の手間と心配を減らしておきましょう。
この記事では、「書く/書かない」の違いを肩の力を抜いて一緒に見ていきます。
遺言書を書く人と書かない人の違い

結論から言えば、50代からは「書く人」になるのが、家族みんなにとって最も楽で現実的です。
遺言書は、これからの家族関係と資産の使い方をデザインする計画書。
書く人は、家族の負担を先回りして減らし、資産を機能させ、トラブルの芽を摘みます。
書かない人は、法定相続という自動配分に委ねつつ、複雑な事情(不動産・再婚・デジタル資産・事業など)ほど不公平と停滞リスクを抱えがちです。
遺言書を書く人の特徴
書く人は、「家族の時間と気持ちの負担を、元気なうちに少しでも減らしておこう」と考えます。
完璧を目指すより、まずは今の方針を言葉にしておくことが大切です。
公平さだけでなく納得感まで含めて整えるために、なぜその配分にしたのかを短いメッセージで添えることも多いです。
丁寧に整えた情報は、とても役に立ちます。
預貯金や証券、保険、不動産に加え、ネット銀行や会員サイトのID・連絡先、ポイントやサブスクまで、思い出せる範囲でメモにまとめると良いでしょう。
紙でもクラウドでも、家族が見つけやすい場所に置いておく工夫をします。
家族関係への配慮も先回りできると最高です。
再婚や連れ子、単身、介護を担う子がいるといった事情を前提に、「誰に、何を、どのように託すか」を具体的に書き分けます。
結果として、相続手続きが止まりにくい設計になります。
不動産は共有化で意思決定が止まりやすいことを理解し、具体的な分け方や代償金、管理者・承継者まで決めておきましょう。
デジタル資産は、連絡先や解約の手がかりを残しておくことで家族の負担を軽くします。
さらに、実行の司令塔も決めておくと家族は大助かりです。
遺言執行者を指定し、連絡先や手続きの大まかな順番を書いておくことで、亡くなった直後の混乱を小さくします。
遺言書を書かない人の特徴
書かない人は、「そのうち家族で話し合えば大丈夫」「うちは揉めないはず」と考え、問題を先送りしがちです。
配分は法定相続の自動配分に任せるため、一見シンプルですが、事情が複雑になるほど不公平感が出やすくなります。
情報は頭の中や通帳・書類の束に散らばりやすく、IDや連絡先が共有されていないことも珍しくありません。
いざという時、口座凍結や名義変更の初動で手間取り、家族が時間と労力を多く割くことになります。
家族関係の調整も事後になります。
再婚・連れ子・単身・介護の偏りなどがあると、話し合いが長引きやすく、気持ちの行き違いが大きくなりがちです。
資産面では、不動産が共有になって売却や活用の意思決定が止まったり、事業の承継が遅れて日常運営に影響が出たりします。
デジタル資産やサブスクは手がかりがなく、解約・整理が難航しがちです。
また、誰が仕切るのかが決まっていないため、初動から主導権の探り合いになり、結果として時間と費用の負担が増えることがあります。
遺言書を書くメリット

- トラブル予防とスピード対応:配分・手続の指示があるため、相続人間の不公平感や長期化を抑え、名義変更等が進みやすい。
- 不動産・事業の止まらない化:共有や意思決定の停滞を避け、活用・売却・承継を円滑に。
- 配慮したい相手へ確実に届ける:配偶者・連れ子・内縁のパートナー・介護を担った子・社会貢献先などへ遺贈が可能。
- デジタル時代への適合:ネット口座やポイント、サブスクの扱いを明記し、探索・解約の負担を軽減。
- 遺言執行者の指定で実行力:第三者や専門職を司令塔にし、手続きを一気通貫で進められる。
- 心理的安心と家族コミュニケーション:付言(メッセージ)で意図や感謝を伝え、理解と納得を得やすい。
- 方式の安全性を選べる:公正証書遺言なら要件不備や紛失リスクが低く、原本保管で長期の安心。
遺言書の書き方と基礎知識

ここまで読んで、遺言書を書いてみたくなった方へ。
「よし、書いてみよう」と思った今が、いちばんの始めどきです!
難しく考えすぎず、「いま決められる範囲で形にする」を合言葉に進めましょう。
まずは全体の流れ(5ステップ)
- 棚卸し:資産・負債・保険・不動産・デジタル資産をリスト化(ざっくりでOK)
- 方針メモ:誰に何をどう託したいか、理由もメモ
- 方式選び:自筆証書 or 公正証書
- 下書き→確認:書式・要件をチェック(専門家の目を入れると安心)
- 保管と共有:保管場所を決め、信頼できる人に「どこにあるか」を伝える
遺言書の方式の選び方
- 自筆証書遺言:手軽/費用低め。全文は自書(※財産目録はPC作成やコピー可・署名押印が必要)。法務局の保管制度を使うと紛失防止と検認不要で実務はぐっと楽に。
- 公正証書遺言:公証人が作成・原本保管。要件ミスが起こりにくく、長期保管も安心。証人2名が必要(専門家手配で解決可)。
迷ったら、ケースが複雑(不動産・事業・再婚・連れ子・単身など)ほど公正証書を推奨します。
シンプルな内容なら、「自筆+法務局保管」で十分実用的です。
【まとめ】専門家と一緒に作ると安心!
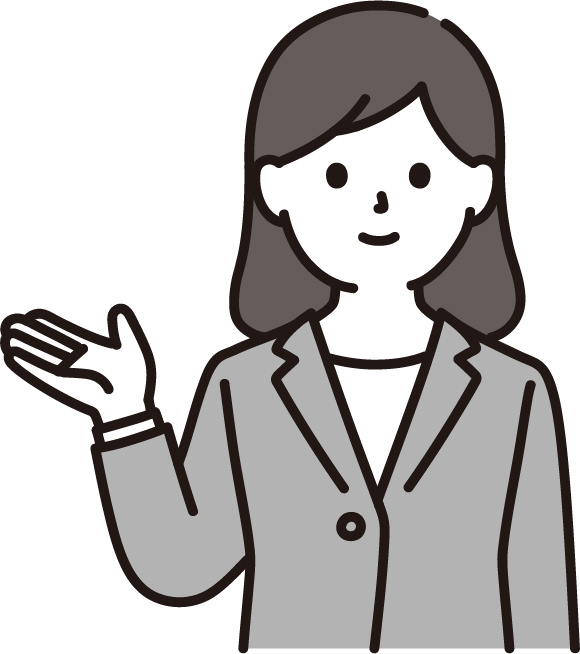
遺言書は、まず気楽に準備を始めましょう。
資産や負債の情報を整理しつつ、家族への配慮を考えます。
もし、難しいと感じて手が止まってしまったら、ぜひ専門家に問い合わせてみましょう。
当事務所では、遺言書の作成をトータルでサポートいたします。
詳しくは、こちらのホームページをご覧ください。

