認知症でも有効な遺言書を作成できる?

認知症であっても、遺言能力があれば遺言書を作成できます。
遺言能力とは、「遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力」です。
認知症の進行度によっては、遺言能力がないと判断される場合があります。
遺言能力の有無の判断には、医学的な診断だけでなく、法律的な判断も必要です。
認知症の方が遺言書を作成する際のポイントは、以下の4つです。
1.遺言能力があるうちに作成する

遺言能力があることの要件は、「15歳以上であること」の他に、「物事に対する判断能力(意思能力)があること」とされています。
認知症と一口に言っても、「不安・抑うつ・物忘れ」などの軽い症状から「幻覚・徘徊・人格変化」などの重い症状まで、さまざまな状況があります。
時間が経過するほどに症状が悪化することが多いため、認知症と診断されたら、できるだけ早く遺言書を作成しましょう。
本来であれば、認知症と診断される前に遺言書を作成するのが望ましいです。
2.公正証書遺言にする
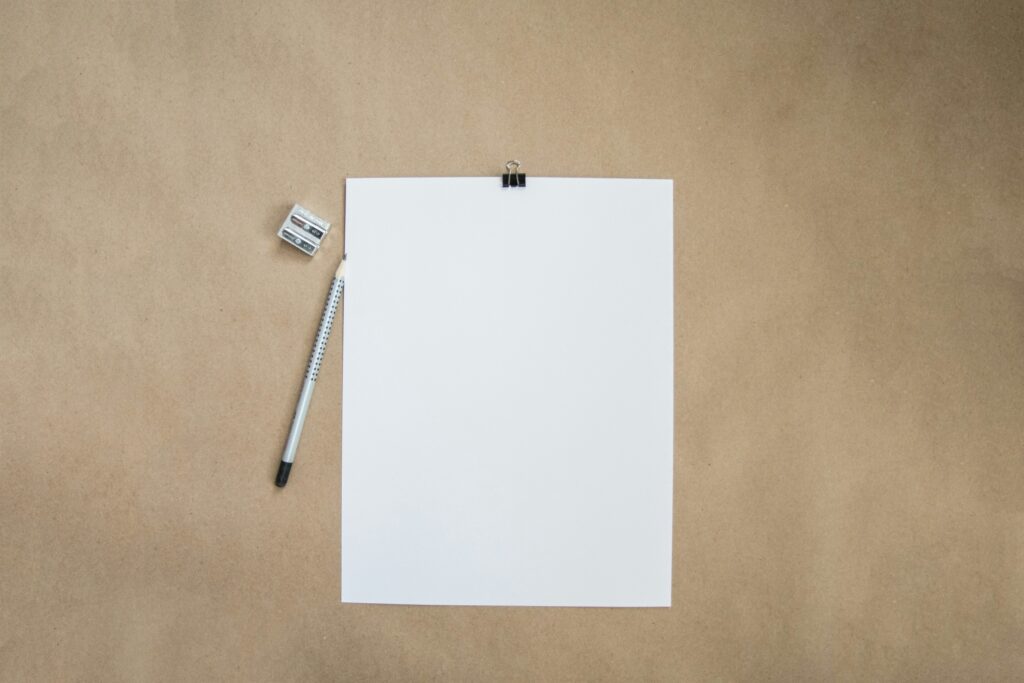
公正証書遺言は、公証人が遺言者の遺言能力を確認するため、自筆証書遺言よりも有効性が高いです。
公証人が文章を作成するため、形式不備で無効になる可能性も基本的にありません。
遺言能力をめぐる争いを避けるには、公正証書遺言がおすすめです。
費用や手間がかかりますが、確実に遺言を残すことができます。
3.遺言執行者を指定する
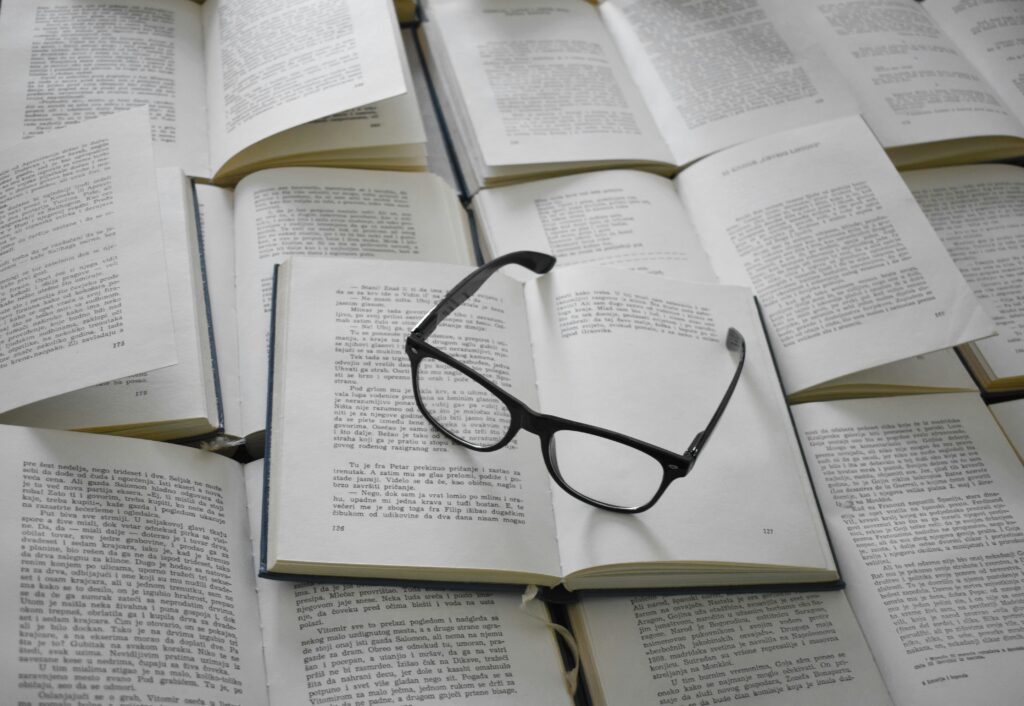
遺言の内容を確実に実行するために、信頼できる遺言執行者を指定しましょう。
遺言執行者とは、「遺言の内容を実現するために一定の職務・権限を与えられた人」です。
相続人の誰かでもいいですし、行政書士や弁護士などの士業に依頼することもできます。
公正証書遺言を作成し、その中で遺言執行者を指名しておくのがおすすめです。
4.遺言能力の証拠を残す

医師の診断書や認知機能テストの結果など、遺言能力があったことを示す証拠を残しておきましょう。
遺言作成の過程や日常生活の様子を動画で撮影しておくと、遺言作成時の遺言者の意思表示が明確であることを示すのに役立ちます。
公正証書遺言では、公証人や証人の立会いによって遺言能力が証明されます。
遺言能力の有無で争わないで済むので、認知症の方には公正証書遺言がおすすめです。
【まとめ】認知症なら公正証書遺言を!
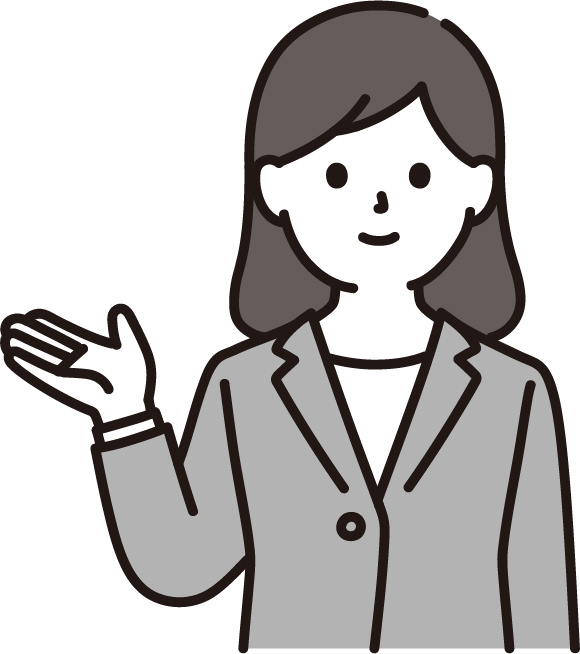
認知症であっても、遺言能力があると認められれば、その遺言は有効です。
しかし、遺言能力の有無を判断するためには、さまざまな証拠が必要となります。
認知症の方には、公正証書遺言がおすすめです。
認知症と診断されたら、早めに公正証書遺言を作成しましょう。
専門家のサポートを受ければ、手続きがスムーズです。
当事務所では、遺言書の作成をトータルでサポートします。
詳しくはコチラでご確認ください。

