2025年問題とは?今すぐ始めたい「遺言書」で家族を守る方法

2025年問題にまつわる社会課題
「2025年問題」という言葉を聞いたことがありますか?
日本でどのような問題が起こると考えられているのかを知っておきましょう。
2025年問題とは何か?
「2025年問題」とは、団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となることです。
社会保障費が急増し、日本社会に大きな影響を及ぼすと言われています。
労働力人口が減少するため、経済成長率の低下も心配です。
家族単位での相続の問題が複雑化し、それに伴うトラブルも増えると予測されています。
相続の増加
日本の高齢化は急速に進み、2035年には60代以上の金融資産保有率が全体の約70%に達すると言われています。
近い将来、多くの親世代が亡くなることで大量の資産が次世代へ相続される「大相続時代」が訪れるでしょう。
また、独身世帯や相続先のない世帯が増えることで、相続にまつわる社会問題がますます顕在化することが予測されます。
老老相続の問題
相続を受ける側も高齢であるという状況を「老老相続」と言います。
例えば、親から子への資産相続で、子もすでに後期高齢者というケースが増加しています。
相続人自身が健康を損ない適切な意思決定ができないことが問題となりやすいです。
また、相続財産の管理能力が不足することから、トラブルが深刻化することもあります。
約74.2%の人が老老相続について認識していないというデータがあり、事前の準備の重要性が叫ばれています。
遺言書が重要な理由

遺言書は安心をもたらす
遺言書は、人生の最期を見据えた重要な意思表示と言えます。
被相続人(故人)は、遺言書を残しておくことで「自分の意思が明確に伝わる」という安心を得ることが可能です。
一方で、相続人(家族)にとっても「故人の意思を尊重する形で相続が進む」という点で安心感があります。
また、精神的だけでなく実務的にも、相続手続きにおける家族の負担を減らすという効果もあります。
遺言書がないとリスクを招く
遺言書が存在しない場合、法定相続分に基づいて遺産が分配されます。
しかし、具体的な分配方法をめぐって意見の対立が生じたり、認識のずれが原因で手続きが滞るケースが多々あります。
相続に関するトラブルの大部分は、遺産分与に関する不公平感や認識の違いから生じています。
老老相続が増える中、認知症患者の法的判断能力が問題となるケースも増加しています。
このような状況を防ぐためにも、生前に遺言書をしっかりと作成しておくことが重要です。
遺言書の種類とその特徴

自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら全文を手書きし、署名押印を行う形式の遺言書です。
メリットは、作成時に費用がかからないことや思い立った時に手軽に作成できる点です。
また、完全にプライバシーを保ちながら、自分の意思を文章として残せるため、第三者の関与を必要としません。
しかし、自筆証書遺言には注意すべき点もあります。
形式不備や内容の不明確さが原因で無効と判断されるケースが多いため、法的な要件をきちんと満たすことが重要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言の内容を確認し、法的に有効な形式で作成する遺言書です。
メリットは、公証人によって作成されるため、無効になるリスクがほとんどない点です。
また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクを回避できます。
作成には証人が2名必要で、公証人手数料がかかることに注意が必要です。
老老相続の増加や相続トラブルのリスクを考えると、公正証書遺言は非常に有効です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言者が作成した遺言書を封印し、公証人および証人の前で、自分の遺言であることを確認してもらう形式です。
この形式は内容を秘密にしたい場合に有効ですが、公証人は遺言内容を確認しないため、内容の法的有効性は保証されません。
後になって、形式や内容が原因で無効とされる恐れがあります。
実際、秘密証書遺言を作成する人は多くありません。
遺言書作成の6つのポイント

1.遺言書作成のタイミング
遺言書作成は、日常生活の中で「今が適切」と感じられるタイミングを逃さないことが大切です。
人生の節目となる年齢や病気の診断をきっかけに作成すると良いでしょう。
50代や60代といった節目の年齢に達した際に、将来的な備えとして検討を始める方が多いです。
また、2025年には後期高齢者における認知症患者が5人に1人になると予測されています。
そのため、健康なうちに自身の意思を明確にしておくことが重要です。
2.家族との話し合い
遺言書の作成にあたっては、まず家族と話し合いを進めることがポイントです。
しかし、実際には、遺言書や相続について話し合いを行っている家庭は少ないという実情があります。
例えば、70代における調査では「遺言についてすでに話している」という割合が約15%に留まる結果が出ています。
話し合いを進める際には、相続内容を一方的に伝えるのではなく、家族それぞれの希望や意向を共有し、具体的な方針をすり合わせることが有効です。
これにより、遺産分配におけるトラブル防止や家族の精神的安心感が得られます。
3.専門家の活用
遺言書の作成は、専門的な知識を要することが多いです。
特に相続人や資産の状況が複雑である場合には、専門家に相談しながら進めると安心です。
専門家ならではの知見を活用すれば、遺言内容が法的に有効であることを確認できます。
また、遺言執行者の選任や遺留分侵害の予防など、相続トラブル回避に向けたアドバイスを受けることで、より円滑な相続準備を行うことができます。
4.遺言執行者の選任
遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実現するために選任される人物のことです。
遺言書に記載された財産分配や手続きをスムーズに行う責任があります。
遺言執行者として選ばれるのは、多くの場合、それにふさわしい信頼できる親族や専門家です。
特に近年では、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼することが増えています。
トラブル防止の観点からも遺言執行者の選任は非常に重要です。
5.トラブルの防止
遺言書作成時には、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。
①遺言能力がしっかりとあるうちに作成することが大切です。
認知症などによって判断能力が低下した段階で作成された遺言は無効となる可能性があります。
②遺留分という法定相続人の最低限の権利に配慮することも重要です。
③公正証書遺言を利用することで、無効になることや遺言書の紛失・改ざんのリスクを避けることができます。
6.定期的な見直し
遺言書を作成した後も、定期的に見直すことが必要です。
家族構成や財産状況の変化に伴い、遺言書の内容が現在の状況と適合しなくなることがあります。
見直しを行うことで、内容が現実に即したものとなり、後のトラブルを防止できます。
5~10年ごとの見直しを目安に、必要に応じて専門家に相談するのがおすすめです。
遺言書作成に必要なこと
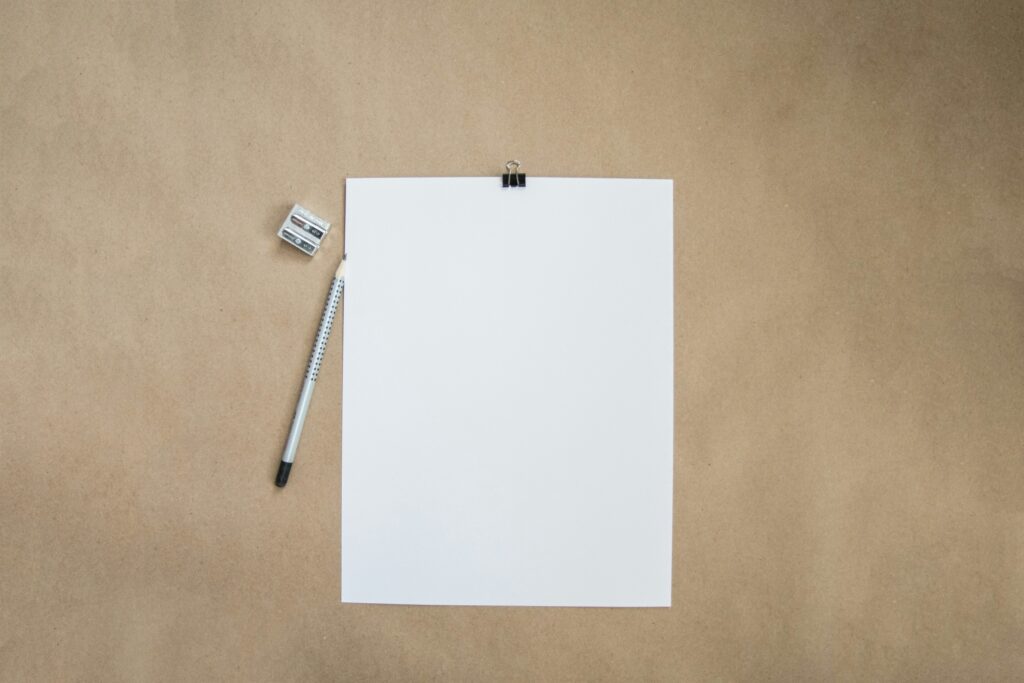
準備すること
遺言書作成を具体的にどのように始めたらよいのかを解説します。
①自分の財産状況を正確に把握しましょう。
預貯金や不動産などの大きな資産に加え、車・保険契約・有価証券なども対象です。
②相続人が誰になるのかを確認しましょう。
法定相続分だけでなく、どのように遺産を分けたいかという希望を明確にすることが重要です。
③遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の特徴を理解し、自分に合った形式を選びましょう。
準備のポイント
高齢の方が遺言書を作成する際には、いくつかのポイントを押さえて準備を進めましょう。
①健康状態が安定している時期に取りかかることが重要です。
認知症などのリスクを踏まえ、遅くとも後期高齢者となる前に取り組むことを推奨します。
②家族と事前に話し合いを持つことも大切です。
遺言の存在や内容について家族間で理解が得られていれば、後の相続が円滑に進む可能性が高まります。
③必要な書類や情報を整理することが求められます。
土地の登記簿謄本や金融資産の明細などを準備しておくとスムーズに進められるでしょう。
【まとめ】遺言書作成は専門家へ!
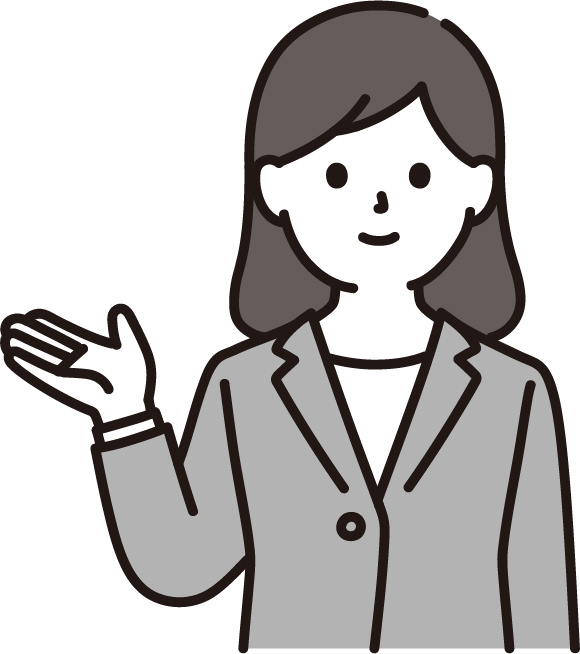
2025年問題は、高齢者だけでなく、すべての世代に関係があります。
相続に関しては、遺言書の作成がもっとも効果的な解決策の1つです。
遺言書はご自身だけでも作成できますが、専門家の力を借りると非常にスムーズです。
当事務所では、遺言書作成をトータルでサポートします。
詳しくはコチラをご確認ください。

