養子縁組と相続について解説!メリットと注意点とは?

養子縁組とは、法律上の親子関係を築く制度です。
養子は実子と同じく、養親の「子」としての法的な権利や義務を持つようになります。
家族のつながりを強める目的だけでなく、相続や税務対策の観点からも注目されています。
養子縁組には民法上の要件があり、たとえば養子になる人が成人していれば、本人の同意が必要です。
未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要なこともあります。
手続きは市区町村役場への届出が基本ですが、「特別養子縁組」を選ぶ場合は家庭裁判所の審判が必須となります。
普通養子縁組と特別養子縁組のちがい

養子縁組には以下の2種類があります。
- 普通養子縁組
養親との親子関係を築きつつ、実親との関係もそのまま残ります。したがって、養子は養親・実親の両方から相続権を持つことになります。 - 特別養子縁組
主に虐待や育児放棄など、子の福祉を守る目的で用いられる制度です。この場合、実親との親子関係は完全に消滅し、養親のみが法的な親になります。
養子は法定相続人になる!

養子縁組を結ぶと、養子は法律上の「子」として法定相続人に含まれます。
法定相続人には、配偶者や血族(子、親、兄弟姉妹など)が含まれ、養子もこれに加わることになります。
注目すべきは、相続税の基礎控除額が増えるという点です。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、養子を迎えることで控除額が大きくなり、結果として相続税が軽減されます。
ただし、税法上で基礎控除の対象とされる養子の数には制限があることに注意が必要です。
- 実子がいる場合:養子1人まで
- 実子がいない場合:養子2人まで
養子縁組がもたらす法律効果

養子は養親との間に、実子と同様の法的な親子関係が成立します。
そのため、次のような効果が生じます。
- 相続権を持つ
- 扶養義務を負う
- 遺産分割では他の子と平等に扱われる
ただし、普通養子縁組か特別養子縁組かによって相続の範囲は異なります。
- 普通養子縁組:実親・養親双方から相続を受けられる
- 特別養子縁組:実親との関係は消滅し、養親からのみ相続できる
養子を法定相続人に含めることで遺産分割がスムーズに進むこともありますが、トラブルが起こるケースもあるため注意が必要です。
相続税対策としての養子縁組のメリット

①相続税の基礎控除額アップ
養子縁組によって法定相続人が増えると、基礎控除が拡大し、相続税の負担が軽くなることがあります。
たとえば、相続人が1人増えれば、控除額は600万円増えます。
ただし、前述のとおり控除に使える養子の人数には制限があるため、節税目的で養子縁組を検討する際は、必ずこの上限を確認しておきましょう。
②「一代飛ばし相続」で二重課税を回避
孫を養子にすることで、親を介さずに祖父母から直接相続させる「一代飛ばし相続」が可能になります。
これにより、本来は「親→子→孫」と2回課税される相続税を、1回に抑えられる可能性があります。
ただし、孫を養子にする場合には、相続税が2割加算されるケースがあるため、かえって負担が増すこともあります。
慎重に検討し、専門家のアドバイスを受けながら進めると安心です。
養子縁組をめぐる注意点とリスク

①相続税がかえって増えることも
養子縁組をしても、すべての場合で節税につながるとは限りません。
2割加算の規定や養子の人数制限によっては、かえって相続税の負担が増えることもあります。
制度の仕組みをよく理解することが欠かせません。
②相続トラブルの火種になることも
養子が増えると相続人も増えるため、遺産分割で実子と養子の間にトラブルが生じる可能性があります。
実子の相続分が減ることで、不満を持つケースもあります。
こうした問題を防ぐには、遺言書を作成して相続内容を明確にしておくことが効果的です。
また、生前に家族間での話し合いを行うことも重要でしょう。
③養子縁組の解除は簡単ではない
一度成立した養子縁組を解消するには、正当な理由と家庭裁判所の許可が必要です。
感情的にも法律的にも大きな影響があるため、安易な判断は禁物です。
養子縁組を行う前に、長期的な関係や相続計画を見据えて慎重に検討しましょう。
行政書士に相談するメリットとは?

養子縁組を相続税対策として検討する際、手続きの進め方や書類の準備に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
そんなとき、行政書士に相談することで、以下のようなサポートを受けることができます。
書類作成と手続きのプロによる支援
行政書士は、戸籍の取得や養子縁組届の作成、相続関係説明図の作成など、正確な書類作成を得意とする国家資格者です。
普通養子縁組の届出や相続税対策を踏まえた書類整理など、実務に即した支援が受けられます。
相続や遺言とのトータルなアドバイス
養子縁組は、単なる家族関係の変化だけでなく、相続税の軽減や遺産分割にも大きく関係します。
行政書士は、相続や遺言書作成の実務経験を活かして、全体のバランスを見ながらサポートできる点も強みです。
ただし、相続税についての助言はできませんので、税理士への相談が必要です。
家庭裁判所案件は弁護士と連携
特別養子縁組や相続トラブルなど裁判所が関与する場面では、行政書士が家庭裁判所に書類を提出することはできません。
しかし、行政書士にまず相談することで、どこまでが自分でできて、どこから弁護士に任せるべきかが明確になり、安心して次の一歩が踏み出せます。
【まとめ】養子縁組の活用は専門家と一緒に!
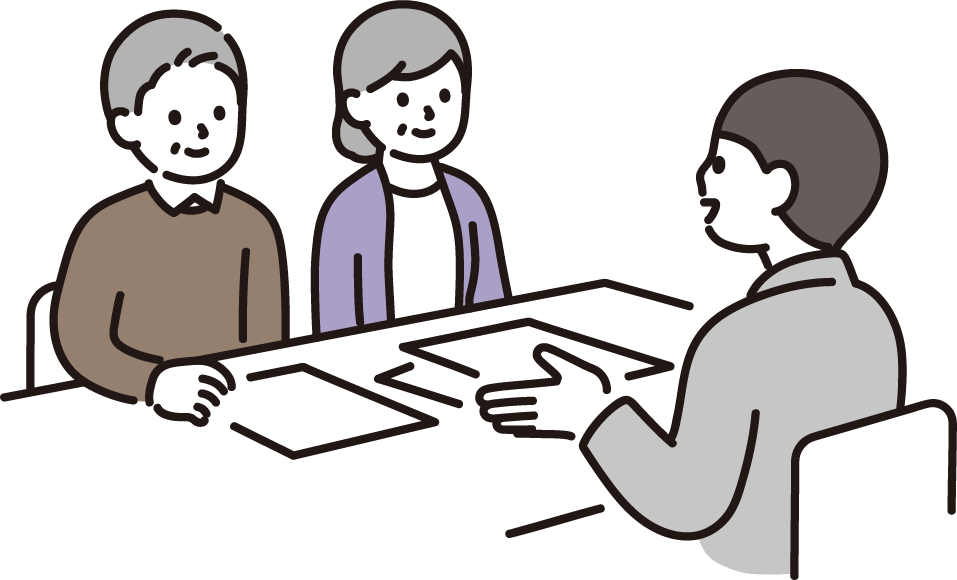
養子縁組は、家族の絆を深めるだけでなく、相続税の節税やスムーズな遺産分割にもつながる制度です。
しかし、法律や税務の知識が不足していると、思わぬ不利益やトラブルに発展することもあります。
だからこそ、行政書士・弁護士・税理士などの専門家への相談が欠かせません。
早めに相談をすることで、手続きミスを防ぎ、安心して養子縁組を進めることができます。
将来の相続に備えて、家族と話し合いながら計画的に取り組みましょう。

